2025年9月27日(土)18時よりテレビ朝日で放送される「人生の楽園 島に笑顔を!瀬戸内の小さな食堂」は、愛媛県今治市・岡村島を舞台にした物語です。番組では会社員を辞めて島へ移住し、地元の食材をふんだんに使った食堂「関前食堂(せきぜんしょくどう)」を営む加藤成崇(しげたか)さんと千晴(ちはる)さん夫妻の暮らしが紹介されます。とれたての魚や柑橘を取り入れた料理は観光客にも島の人々にも親しまれ、さらに高齢者へ弁当を届ける活動やミカン畑の復活など、地域に根ざした取り組みが描かれます。
岡村島は瀬戸内の温暖な気候に恵まれた小さな島で、美しい海と自然が広がる一方、人口減少や高齢化といった課題を抱えています。そんな島で「食」を通じて人と人とをつなぎ、笑顔を広げていく夫妻の挑戦は、同じように地方移住や地域活性化に関心を持つ人々にとっても大きなヒントとなるでしょう。
関前食堂の基本情報 ― 所在地・電話・アクセス・運営など
名称:関前食堂
所在地:愛媛県今治市関前岡村甲852-4
電話:09072115571
営業時間:10:30〜15:00(土・日・祝) 11:30〜13:30(水・木・金)
定休日:月・火曜
facebook:関前食堂
instagram:sekizen.shokudou
関前食堂は愛媛県今治市関前岡村甲852-4にあります。岡村島の港から歩いて3分ほどの場所です。海が近く景色が開ける立地です。建物は大正期の迎賓館を活用した趣ある空間です。木の梁や扉の質感が残り落ち着いた雰囲気です。電話は090-7211-5571です。問い合わせや予約の相談に便利です。2020年4月に開業し島の日常に寄り添う食堂として親しまれてきました。島外の来訪者にも道案内がしやすい場所です。港が目印になります。
営業時間は土日祝が10:30〜15:00です。平日は水曜から金曜が11:30〜13:30です。月曜と火曜はお休みです。仕入れや仕込みの都合で変わる日があります。出発前に最新情報を確認すると安心です。店内は全席禁煙です。小さな子ども連れや年配の方にも過ごしやすい環境です。支払いはクレジットカードや電子マネーやコード決済に対応します。島内では貴重な選択肢です。自転車スタンドがありサイクリストにも寄り道しやすい設えです。港周辺に駐車の案内があります。フェリーで岡村港に着いたら海沿いを歩けば迷いません。島の掲示や地図も役に立ちます。
公式の発信は主にフェイスブックやインスタグラムです。営業日や臨時のお知らせや新しい料理の写真が分かります。島の行事や漁の話題が登場することもあります。初めての方は外観や席数の雰囲気が伝わります。島の食材の入荷状況も知ることができます。遠方から向かう方は天候や船の運航状況も合わせて確認すると安心です。岡村島へは今治エリアからの船便が便利です。港を降りたら潮の香りに包まれます。歩道は平坦です。年配の方も移動しやすい距離です。島時間でゆっくり過ごせます。景色を眺めながら向かう道のりもこの店の魅力の一部です。到着したら深呼吸をして席に着きます。海と島の恵みに出合う準備が整います。
瀬戸内の魚と島の恵みを生かす小さな食堂
食堂の料理はとれたての魚と季節の野菜と島の柑橘を軸に組み立てます。日替わりで内容が変わります。朝の入荷で献立が動きます。漁の具合で魚種が変わります。脂の乗りや身の締まりに合わせて火入れや味付けを調整します。丼や定食やカレーの形に落とし込みます。塩分は控えめで香りと食感で満足感を高めます。副菜は海藻や煮物やサラダで構成します。食べやすさと栄養のバランスを意識します。ご飯は盛りを選べます。高齢の方や子どもにも無理のない量に調整します。仕込みは無駄を出さない順番で進めます。余剰は翌日の一品に転換します。価格は島の暮らしに寄り添う設定です。観光シーズンは早い時間に売り切れる日があります。開店時間に合わせて訪ねると安心です。店内は港に近く窓から光が入ります。料理の湯気と潮の香りが重なります。漁師さんや農家さんとのやり取りが日々の品質を支えます。顔の見える取引は信頼を育みます。旬の柑橘が香る一皿は瀬戸内らしさを素直に伝えます。観光客に人気の理由は味だけではありません。迷わず歩ける立地と気負わない接客と清潔な店内がそろいます。写真より先に香りが記憶に残ります。食べ終えたあと港の風に当たる時間までが体験になります。料理が地域の人の笑顔をつなぎ遠方から来た人の再訪の理由になります。店は小さいからこそ柔軟に変わり続けます。季節が回るたびに同じ料理でも新しい表情に出会えます。
人気メニュー紹介
関前食堂の看板は島レモンのバターチキンカレーです。瀬戸内の明るさを思わせる香りが立ちのぼります。濃厚な旨みの中に爽やかな酸味がすっと通ります。辛さは穏やかでコクがあります。島の柑橘とスパイスの橋渡しが心地よいです。海を見ながら食べるとさらにおいしく感じます。観光の1皿にも日常の1皿にもなる包容力があります。ご飯の量や副菜の配置が整い最後のひと口まで飽きません。写真映えしますが味が主役です。スプーンが自然に進みます。
ひじきの柑橘まぜうどんは島らしさが詰まった1品です。磯の香りが穏やかに広がります。柑橘の爽快さが後味を軽くします。暑い日も寒い日も素直においしい口当たりです。油は控えめで胃にもやさしいです。時期によって柑橘は変わります。旬の表情がそのまま届きます。小さめのバターチキンと合わせる提案が出る日もあります。組み合わせで満足感が増します。麺のコシと具の食感の対比が楽しいです。島の乾物と果実の相性を確かめられます。
海鮮丼はその日の海の機嫌で顔ぶれが変わります。瀬戸内の地魚が主役です。白身の甘さや青魚の香りや貝の歯ざわりが交代で現れます。漁の内容で盛りが変わるため早めの時間帯が安心です。丼つゆは控えめで素材を立てます。薬味で味を重ねます。港町ならではの満足感があります。旅の予定に合わせて立ち寄る人が多いです。地元の常連も定期的に選ぶ定番です。
合い盛りカレーは2つの味を1皿で楽しめます。バターチキンのまろやかさとキーマの香味が交互に来ます。辛さの階段を上がる楽しさがあります。レモンを絞ると表情が変わります。副菜と合わせるとさらに広がります。島の野菜が脇を固めます。食べ終わる頃には香りと記憶が重なります。
いずれの料理も仕入れと季節で姿を変えます。数量限定の日があります。売り切れの案内が出ることがあります。遠方からの方は開店直後の来店が安心です。最新の発信で当日の様子を確かめるとよいです。水分補給をしながら並ぶ準備も整えます。島の時間に合わせて急がず楽しみます。食べ終えたあとは港の風に当たります。器の余韻と海の気配が残ります。料理は島の暮らしとつながります。食べる人の笑顔が次の1皿を生みます。島の記憶として積み重なります。
高齢者への弁当宅配という地域貢献
関前食堂では開店当初から高齢者への弁当宅配に力を入れています。島には車を持たない方や足が不自由で外出が難しい方が多くいます。スーパーや病院までの距離があり船便やバスの本数も限られているため日々の買い物や調理に負担を感じる声がありました。加藤さん夫妻は自分たちの料理で少しでも暮らしを支えたいと考え弁当づくりを始めました。
宅配を始めた背景には地域への恩返しの思いがあります。島に移住した時から多くの人に助けられた経験があり今度は自分たちが役に立ちたいと願いました。お弁当は魚や野菜を中心にした栄養バランスのよい内容で塩分を控えめにし柔らかさにも気を配っています。利用するお年寄りは「温かいご飯を届けてもらえるのが何よりうれしい」と話し会話の時間を楽しみにしている方もいます。食事と同時に安否確認にもつながるため家族にとっても安心です。
この取り組みは小さな島で安心して暮らし続けるための大切な一歩です。高齢者が笑顔で過ごせることは島全体の元気にもつながります。宅配は単なる食の支援にとどまらず人と人との結びつきを深め孤立を防ぐ役割も果たしています。島で暮らすことの安心感を支える基盤となり移住者と住民の信頼関係を強めています。
加藤成崇さんと千晴さん夫妻の移住ストーリー
加藤成崇さんと千晴さんは会社員として働いたのち生き方を見直しました。病気をきっかけに時間の使い方と働き方を根本から考え直しました。自分の手で食を作り顔の見えるお客さまに届けたいという願いが強まりました。夫婦で話し合いを重ね準備を進めました。休日に各地の島を歩き暮らしの規模や物件や移動手段を確かめました。島の人と丁寧に会話を重ねました。暮らしの現実を聞き取りました。一定の貯えと開業計画を整えました。必要な設備や資格や仕入れ先を順に固めました。岡村島の建物に出会い可能性を感じました。改修は地域の力を借りました。木部を磨き厨房を整え動線をつくりました。道具は必要最小限にしました。開業後は朝の仕入れと下ごしらえと配達の段取りを見直し続けました。島の生活リズムに自分たちの仕事を合わせました。行事や天候で来客が変わるため柔軟にメニューを切り替えました。高齢の方の食べやすさにも配慮しました。味や量や価格の折り合いを探りました。夫婦で役割を分けました。片方が接客に立ち片方が調理を支えました。日々の対話を欠かしませんでした。島で暮らすからこそ顔が見える関係が支えになります。困った時に助けを求められる関係が広がります。夫婦の選択は生活の改善と地域の安心の両方に寄与します。
舞台は瀬戸内・岡村島
岡村島は愛媛県今治市に属する小さな島です。海に抱かれた静かな集落が続きます。港を中心に道が緩やかに伸びます。橋で広島県側とつながる安芸灘とびしま海道の終点近くに位置します。車や自転車で島々を渡りながら訪ねられます。今治からはフェリー便もあります。海上の移動は天候に左右されるため発着の確認が役に立ちます。島は温暖で柑橘が育ちます。浜辺の光や潮の香りが日常を形づくります。釣りや小さな畑や縁側の語らいなど素朴な営みが息づきます。観光の派手さはありません。けれども暮らしの基礎がゆっくり見えてきます。買い物や医療や交通は本土に比べ選択肢が限られます。人口減少と高齢化の課題も現実です。空き家や耕作放棄地の維持が家々の負担になります。だからこそ地域の支え合いが生活の質を左右します。外から来た人の新しい視点が役に立つ場面が増えます。小さな商いが島の循環を整えます。観光客は混雑を避け静けさを尊ぶ姿勢が求められます。歩行者と自転車を思いやる速度で過ごします。海と人の距離が近いので挨拶が自然に生まれます。訪れた人も暮らす人も同じ景色を分かち合います。
かつての島の誇り「ミカン栽培」の復活
岡村島はかつて柑橘の栽培が盛んでした。温暖な気候と日当たりのよい段々畑はミカンづくりに適しており最盛期には島の風景をオレンジ色に染めていました。しかし農家の高齢化や担い手不足で畑は荒れ木は剪定されず収穫もできない状態が広がりました。かつての誇りである産業が衰退していく姿は島の人にとって寂しさと課題を感じさせるものでした。
加藤さん夫妻は食堂を営むかたわら空き畑の再生にも挑戦しています。荒れた土地を整備し苗木を植え地域の方の知恵を借りながら少しずつ手を入れていきます。高齢の農家から技術を学び剪定や肥料の工夫を実践します。収穫まで時間はかかりますが島の未来のために続ける価値があります。
この挑戦は単に農産物を増やすだけではなく島の景観を守り地域の誇りを取り戻す意味も持ちます。若い世代や移住者が関わることで次の担い手が育ちます。ミカンが再び岡村島の象徴となれば観光や交流にも広がります。島の未来を支える小さな挑戦がやがて大きな実りを生むことにつながります。
島で暮らすことの喜びと苦労
島暮らしには喜びと同時に現実的な苦労もあります。海や山に囲まれた環境は静かで自然が豊かです。新鮮な魚や柑橘に恵まれ四季を身近に感じられることは都会では得られない魅力です。人との距離が近く挨拶や助け合いが自然に育ちます。日常の中にゆとりがあり時間の流れが穏やかです。
一方で都会とは違う不便さもあります。買い物や病院に行くにも時間がかかり交通手段が限られています。若い人が少なく行事や作業の担い手不足も課題です。移住した人は自分の暮らしと地域のリズムを合わせる努力が求められます。地域の行事に参加し顔を覚えてもらうことで信頼関係が築かれます。
移住を考える人にとって大切なのは理想と現実を両方知ることです。島暮らしは憧れだけでは続きません。しかし人の温かさや自然の恵みを感じながら自分らしい生活を送りたい人には大きな魅力があります。自分の力で生き方を選び人と支え合う環境を求める人にとって島は確かな選択肢になります。
瀬戸内の島に学ぶ「地域循環型の暮らし」
瀬戸内の島には地産地消の暮らしが息づいています。海でとれた魚や畑で採れた野菜が食卓に並び調味料も地元のものを使います。輸送に頼らない循環は新鮮さと安心をもたらし環境負荷も少なくなります。食堂が地域の食材を使うことは生産者の励みになり消費者の健康にもつながります。
高齢者支援の仕組みと若い世代の定住促進が重なると島の循環はさらに安定します。弁当宅配は高齢者の暮らしを守りミカン畑の再生は若い人の働き場を生みます。観光客が食堂や直売所で地元産を選ぶことも循環を支える一部になります。小さな経済の輪が重なり合い地域の持続性を高めます。
持続可能な地域づくりの視点は世界的にも求められています。瀬戸内の島で行われている実践は規模は小さいですが普遍的な価値を持ちます。自分たちの土地の恵みを大切にし顔の見える関係を築くことが安心を生みます。島の暮らしに学ぶ姿勢は都会に住む人にとっても参考になります。環境と人と経済をつなぐ循環型の暮らしはこれからの社会の方向性を示しています。
番組を通じて伝わるメッセージ
今回の放送で大きく浮かび上がるのは恩返しというテーマです。加藤さん夫妻は病気や働き方の転換を経て島に移住しました。そこでは多くの人から支えを受けました。その経験が食堂の運営や弁当宅配に反映されています。自分たちがもらった元気を形に変えて返す姿勢が島の人々の安心につながっています。単なる飲食店の経営ではなく地域全体の暮らしを見据えた取り組みが番組を通して伝わってきます。
安心して住み続けられる島とは食べ物や生活の支援が行き届き孤立しない環境がある場所です。高齢者が弁当を受け取り世間話を交わせる時間は日常の大切な一部になります。若い世代や移住者が農地再生や新しい挑戦に関わることで地域の未来も育ちます。島に住む誰もが役割を持ち安心して暮らせる姿は他地域にも通じる理想の形です。
視聴者にとってこの物語は生き方の選択肢を示します。都会で働くことだけが人生ではなく自分の力を活かし地域に根差して暮らす道もあります。番組は派手な演出を避けることで一歩を踏み出した人の姿をそのまま映し出します。人と人との関係や自然との関わりに価値を見いだす生き方は多くの人に響きます。視聴後に自分の生活を見直し身近な人との関わりを考え直すきっかけになります。
人生の楽園とは?番組の特徴と魅力
人生の楽園は各地で第二の人生に挑む人の暮らしを丁寧に紹介する番組です。地方で店を始める人や故郷に戻る人がどのように地域と関わり日常を築くのかを現地の風景と食とともに伝えます。番組は派手さより実直さを大切にします。だから視聴者は登場人物の言葉やしぐさから等身大の手触りを受け取れます。人生の節目に悩む人や移住や転職を考える人にとって次の一歩を考える材料になります。案内人は菊池桃子さんと小木逸平アナウンサーです。二人は穏やかな語りで主人公の歩みを支えます。説明は要点だけに絞られます。映像と生活音が物語の中心に置かれます。若い世代にも理解しやすい構成です。家族で共有しやすい落ち着いたトーンです。深夜ではなく夕方の時間帯に放送される理由がここにあります。テレビ朝日が青少年に見てもらいたい番組として位置づける背景にもつながります。過度な演出を避け誠実な編集で実像に寄り添います。視聴後に心が少し軽くなるので明日への行動が具体化します。番組をきっかけに地域を訪ねる人も増えます。暮らしを変えるための最初の検索や相談の糸口が生まれます。

まとめ
関前食堂の歩みから学べることは地域に根ざした小さな実践が確かな力になるということです。地元食材を活かした料理は観光客を惹きつけると同時に住民の暮らしを支えています。弁当宅配は高齢者に安心を与えミカン畑の再生は島の未来を照らします。加藤さん夫妻の活動は規模は大きくなくても人々にとってかけがえのない存在になっています。
移住や地域活動への関心を広げるきっかけとしてこの番組は大きな役割を果たします。都会での暮らしに疑問を感じる人や新しい生活を探す人にとって具体的な姿が示されます。成功や失敗を含めた実際の取り組みは現実的な参考になります。視聴者は自分にとって何が大切かを考えるきっかけを得ます。地域と向き合いながら生きる選択は誰にでも開かれています。
人生の楽園が描く地方再生の姿は華やかなプロジェクトではなく一人一人の地道な努力の積み重ねです。小さな食堂が島全体を元気にするように日常の営みが地域を支えます。放送を通じて示される暮らしの形は地方での可能性を広げ未来に希望を感じさせます。都会に暮らす人も地方に暮らす人も自分らしい生活を考える手がかりを得られます。この番組は人と地域を結び暮らしの価値を見直す契機になります。
あとがき|小さな島から広がる笑顔の物語
小さな島に1つの食堂ができただけで、なぜこれほどまでに人の心を動かすのでしょうか。その理由を考えると、単なる飲食店という枠を超えて、人と人のつながりや地域全体の未来にまで光を投げかけているからだと思います。関前食堂の物語には、本文では伝えきれなかった裏側の背景や、もっと大きな視点で見たときの意味が隠れています。ここでは少し肩の力を抜いて、コラム風に感じたことを綴ってみたいと思います。
島の文化と暮らしの裏話
岡村島は瀬戸内海に浮かぶ小さな島ですが、昔から人と海とが深く結びついて生きてきました。船の往来が盛んだった頃には、港町として多くの人が行き交い、島の集会や祭りも大きな賑わいを見せていたそうです。ところが近年は人口減少や高齢化で、かつての賑わいが少しずつ薄れてきました。ミカン畑が荒れていったのも、そうした流れの一部です。
しかし、文化の灯火は完全に消えたわけではありません。島のお年寄りたちが語る昔話や、祭りのときに鳴り響く太鼓の音、そして島特有の方言は今も息づいています。食堂ができたことで、そうした文化が再び人々の暮らしの中に顔を出すようになりました。観光客が訪れ、地元の人と会話を交わし、料理を味わうことで、単なる「食事」ではなく「文化体験」となっているのです。
日本全体の課題と島からのヒント
少子高齢化や人口減少は日本全体が抱える大きな課題です。都市部では介護や医療の不足、地方では担い手不足や空き家の増加など、形は違っても同じ問題が広がっています。その中で岡村島のような取り組みは、一見すると小さな活動ですが、大きな意味を持っています。
弁当の宅配は食を届けるだけでなく、見守りの役割を果たします。これが安心につながり、孤立を防ぎます。畑の再生は農産物を生むだけでなく、地域の誇りを呼び戻します。こうした循環は、都市部にも応用できるはずです。規模は違っても、近所で顔を合わせる関係をつくり直すことが、どこに住んでいても求められているのではないでしょうか。
グローバルな視点から見た島暮らしの価値
少し視野を広げて世界を見渡すと、人口減少や地域の衰退は日本だけの問題ではありません。ヨーロッパの小さな農村やアジアの漁村でも同じような課題に直面しています。そんな中で注目されるのは「地域循環型の暮らし」です。自分たちの土地の恵みを使い、人と人が顔を合わせて支え合う仕組みは、持続可能性という点で大きな価値を持ちます。
グローバル経済の中で大量生産や大量消費が進む一方で、こうした小さな暮らしの循環が世界的に再評価されているのです。岡村島の食堂や畑の取り組みは、国際的に見ても先進的な実践と言えるでしょう。都会の便利さを追い求める生活と、自然と人に寄り添う生活との間で、私たちはこれからの道を選んでいく必要があります。
ユーモアを交えて思うこと
食堂の物語を聞いていると、「人間はやっぱり食べることが好きなんだな」と微笑ましくなります。新幹線も飛行機も便利ですが、最終的にはお腹が空けばご飯に向かうのです。都会でどんなに忙しく働いていても、温かいご飯を食べると心が和みます。弁当を受け取ったお年寄りが「ありがとう」と笑顔になる瞬間、それだけで地域全体の空気が変わるように思えます。
また、ミカン畑を再生する話を聞くと、なんだか昔の少年漫画を思い出します。荒れ果てた畑を一から耕し、実がなり、収穫して笑顔が広がる。その過程はドラマチックでありながら、実際の生活に根ざしています。島暮らしには不便さもありますが、その中に人間らしい喜びや笑いが詰まっています。
応援の気持ちを込めて
関前食堂の物語は単なる地域紹介にとどまらず、見る人に勇気を与えます。「自分にも何かできるかもしれない」「小さな一歩が大切なんだ」と思わせてくれるのです。地方に移住しなくても、自分の地域でできることはたくさんあります。隣の人に声をかける、地元の店で買い物をする、それだけでも地域の力になります。
私はこの取り組みがとても好きです。島で暮らす人々の笑顔や、弁当を手渡すときの温かいやり取りに強く心を動かされます。応援していますと声を大にして伝えたいです。小さな食堂が地域に根を張り、人と人を結び、未来を照らしていく姿は本当に希望の物語です。
岡村島から広がる笑顔の物語は、私たちの暮らしに大切なものを教えてくれます。便利さや効率だけでは測れない価値があり、人と人との関わりの中に本当の豊かさがあります。この小さな島の取り組みが、全国にそして世界に広がっていけば、社会全体が少しずつ温かく変わっていくのではないでしょうか。
笑顔は伝染します。1つの食堂から始まった笑顔が、島を越えて、海を越えて、多くの人に届くことを願っています。私自身もその輪の中に加わりたいと強く感じました。これからも静かに、けれど確かに、この物語を応援していきます。
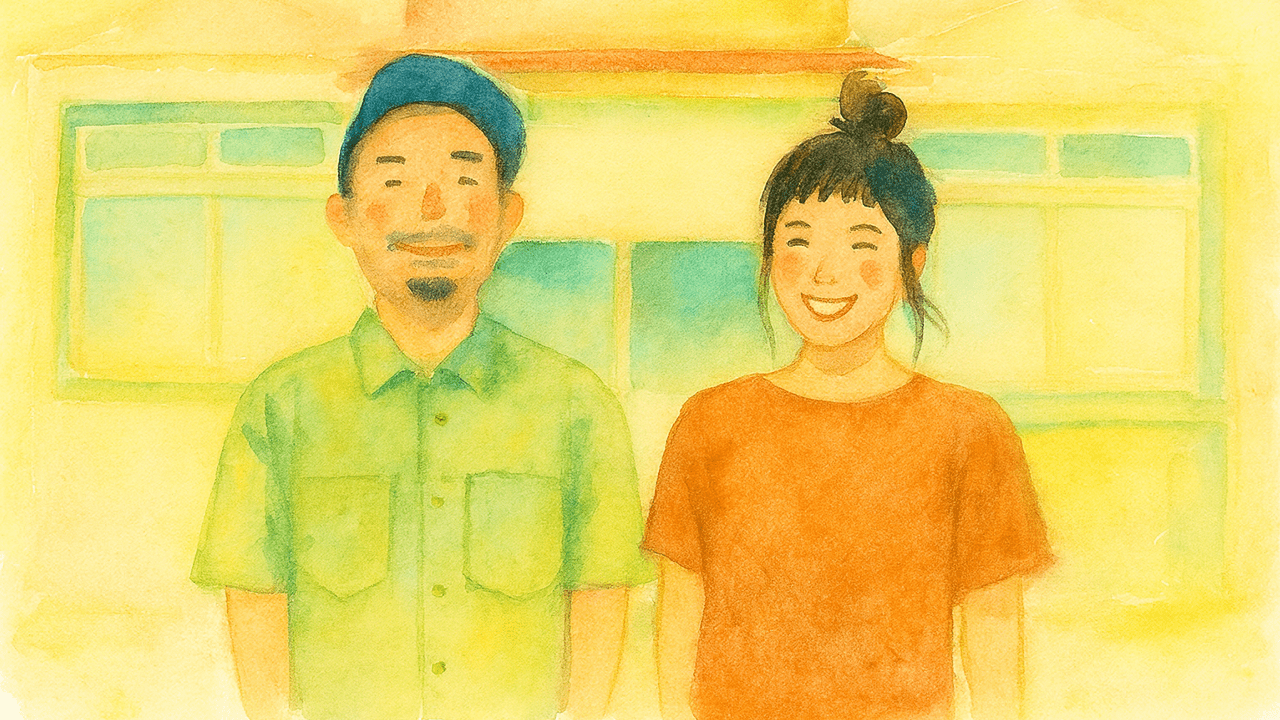
コメント