2025年10月14日放送のNHK「クローズアップ現代」では、全国で利用者が急増している“にぎやかな図書館”の特集です。かつて図書館といえば「静かに本を読む場所」というイメージが一般的でした。しかし近年は、飲食や会話が許可される“にぎやかな図書館”が全国で増えています。背景には、人口減少や地域コミュニティの希薄化にともなう「誰もが安心して過ごせる居場所」への需要があります。今、公共空間としての図書館が再び注目を集めています。
「にぎやかな図書館」とは何か?
にぎやかな図書館とは、おしゃべりや飲食を禁止せず、人と人の交流や滞在を前提に設計された新しいタイプの図書館を指します。従来のように静寂を保つ空間ではなく、学び合い・語り合い・過ごし合うことを目的とした「滞在型図書館」です。利用者は読書をするだけでなく、コーヒーを片手に談笑したり、ワークスペースとして使ったりと自由度が高くなっています。
この動きは単なるトレンドではありません。公共施設の役割が「資料の貸出」から「地域の課題解決・交流の促進」へと変化していることの表れです。孤立防止や高齢者の居場所づくり、子育て世代の交流拠点など、多様なニーズに応える柔軟な空間が求められています。
全国の“にぎやかな図書館”リスト
| 施設名 | 住所・電話 | 公式サイト | “にぎやかさ”要素・ゆるさ導入内容 |
|---|---|---|---|
| みんなの森 ぎふメディアコスモス(岐阜市立中央図書館) | 〒500-8076 岐阜県岐阜市司町40-5 ☎ 058-262-2924 |
公式サイト | “滞在型図書館”を掲げ、館内に談話・交流スペースを設置。イベント・展示・市民活動の拠点として開放。 |
| 那須塩原市図書館 みるる | 〒325-0056 栃木県那須塩原市本町1-1(黒磯駅前) ☎ 0287-63-9031 |
公式サイト | 飲食・会話OKゾーンを設置。カフェ・ギャラリー併設で夜21時まで開館する“駅前にぎわい拠点”。 |
| 石川県立図書館(百万石ビブリオバウム) | 〒920-0942 石川県金沢市小立野2-43-1 ☎ 076-223-9565 |
公式サイト | 「文化交流エリア」など多目的ゾーンを併設し、閲覧とイベントを共存させる開放的空間設計。 |
| 武蔵野プレイス | 〒180-0023 東京都武蔵野市境南町2-3-18 ☎ 0422-30-1900 |
公式サイト | 図書館・学習・市民活動を融合。ワークラウンジ・交流スペースを備え“静と動”を両立。 |
| 日比谷図書文化館 | 〒100-0012 東京都千代田区日比谷公園1-4 ☎ 03-3502-3340 |
公式サイト | カフェ・レストラン併設。持込飲料可で、展示・イベントと連携した多目的利用を促進。 |
| せんだいメディアテーク | 〒980-0821 宮城県仙台市青葉区春日町2-1 ☎ 022-713-3171 |
公式サイト | 図書館・ギャラリー・カフェが融合した“まちに開かれた複合文化施設”。滞在・対話を歓迎。 |
| 川の上・百俵館(石巻) | 〒986-0132 宮城県石巻市小船越字山畑343-1 ☎ 0225-75-2100 |
公式サイト | 旧農業倉庫を改修し“お茶と会話ができる図書館”として再生。地域密着型の温かな運営。 |
| 森の図書室(渋谷) | 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂2-8-2 大和田ビル8F ☎ 03-6455-0629 |
公式サイト | 飲んだり、食べたり、おしゃべりできる“ブックカフェ型図書室”。夜遅くまで営業。 |
なぜ“にぎやかな図書館”が支持されているのか
NHK「クローズアップ現代」で取り上げられるまでに注目を集めた“にぎやかな図書館”の背景には、いくつかの要因が重なっています。単なる話題性ではなく、社会の変化と公共空間の再設計が密接に関係しているのです。
図書館の敷居を下げた「ゆるやかさ」
「静かにしなければならない場所」という固定観念を取り払ったことが、最大の要因といえます。おしゃべりや飲食を許可することで、子育て世代や学生など、従来は足を運びにくかった層が自然に立ち寄れるようになりました。“図書館=利用しづらい場所”という心理的な壁をなくし、“本と人の距離”を近づけた意義は大きいでしょう。ただし、静かな環境を求める人もいるため、音や匂い、座席マナーなど、共存を保つルール設計が欠かせません。
複合施設としての進化
スーパーやカフェ、遊び場を併設するなど、複合的な機能を持つ図書館が増えています。「図書館に行く」だけでなく、「ついでに寄る」「子どもを遊ばせる」「友人と待ち合わせる」といった複数の動線が生まれる点が特徴です。これは、図書館を地域の“生活動線”の中に溶け込ませる設計思想です。ただし、複合性を高めすぎると、本来の静読や資料収集などの図書館機能が薄れる危険もあります。設計と運営で、にぎやかさと専門性の均衡を保つことが求められます。
地域課題との接点づくり
“にぎやかな図書館”が地域で支持される背景には、「まちの課題を共有する場所」としての新しい役割があります。たとえばイベントやワークショップを通じて、子どもの学び支援、高齢者の交流、地域防災など、図書館が地域活動と結びつく事例が増えています。こうした取り組みにより、図書館は“文化施設”から“生活基盤”の一部へと進化しました。ただし、職員の負担や専門外の領域に踏み込むリスクもあるため、外部との連携や協働の体制づくりが欠かせません。
空間デザインと動線計画の巧みさ
にぎやかな図書館の多くは、建築的にも魅力的です。大きな吹き抜けや自然光を活かした構造、居場所の多様化(窓際席・親子席・グループ席など)が利用者の滞在意欲を高めています。建築家やデザイナーが来館者の動線を緻密に想定し、“静”と“動”のゾーンを分けて設計していることも特徴です。
その結果、読書・会話・学習など異なる目的の人々が、互いに気を遣わず過ごせる環境が実現しています。
参加型の企画と発信力
“にぎやかさ”は空間だけでなく、企画や発信の工夫からも生まれます。図書館まつりや読書会、地域ブックトークなど、来館者が参加できるイベントを継続的に行うことで、図書館が「行く場所」から「関わる場所」へと変わります。また、SNSや地域広報を活用した発信も効果的です。地域住民の声を取り入れながら企画を更新することで、“使われる図書館”としての存在感が持続します。
利用者10倍の象徴「みんなの森 ぎふメディアコスモス」
岐阜市の「みんなの森 ぎふメディアコスモス」は、“にぎやかな図書館”の代名詞ともいえる存在です。木造の波打つ天井と、東濃ヒノキを使ったグローブ型の照明が特徴的で、訪れる人を包み込むような温かい空間を演出しています。館内は単なる書架スペースではなく、市民活動やアート展示、講演会などが同時に行われる“共創の場”です。
利用者が10倍に増えた背景には、「静かに読む」以外の行動を肯定した設計があります。飲食・会話ができるゾーンを明確に分け、利用者同士が気持ちよく過ごせるよう工夫されているのです。図書館が地域文化と市民活動をつなげる拠点となった成功例として、多くの自治体が注目しています。
全国で広がる“おしゃべりできる図書館”の潮流
にぎやかな図書館の流れは岐阜だけにとどまりません。栃木県那須塩原市の「みるる」は、カフェやギャラリーを併設した駅前図書館です。夜21時まで営業しており、仕事帰りや学生、子育て世代が立ち寄れる「まちのリビング」として親しまれています。館内には飲食やおしゃべりを楽しめるエリアがあり、滞在時間が大幅に伸びたといいます。
石川県の「百万石ビブリオバウム」も、閲覧と交流を両立させた空間設計が特徴です。開放的な階段状の閲覧エリアでは、学生たちがノートパソコンを広げ、自然光の差し込む中で議論や作業を行う姿が見られます。東京都の「武蔵野プレイス」や「日比谷図書文化館」も同様に、静と動のゾーニングを工夫し、滞在型文化施設として定着しています。
民間・地域発の新しい図書館モデル
公立図書館だけでなく、民間や地域主導による小規模な“にぎやか図書館”も注目されています。東京都渋谷の「森の図書室」はその代表例です。飲みながら読める、食べながら語れるブックカフェ型の図書室として若い世代に人気を集めています。SNSを通じて本好きがつながり、新しい読書文化を生み出している点もユニークです。
宮城県石巻市の「川の上・百俵館」は、古い農業倉庫を改修してつくられた地域密着型の図書館です。「お茶を飲みながら話せる場所」をコンセプトに、地域住民が集う拠点となっています。小規模でも“にぎやかさ”を取り入れた運営で、まちづくりの核となる成功事例といえます。
にぎやかさの裏側:運営と課題|気をつけたい視点・批判的観点
一方で、“にぎやかさ”を重視するあまり、見落としてはいけない課題も存在します。
公平性とアクセス性
静かに集中したい人や、交通の便が悪い地域に住む人にとって利用しづらいケースがあります。都市中心部だけでなく、地方や高齢者にも公平に開かれた設計が必要です。
運営コストと持続可能性
カフェやイベントスペースの維持には人件費・清掃・光熱費など多くのコストがかかります。初期投資だけでなく、継続的な財政支援の仕組みをどう確立するかが課題です。
ルールとマナーの管理
自由度を高めるほど、音や飲食のマナー、席の占拠などのトラブルが増える傾向にあります。誰もが快適に過ごせる環境を守るためには、明確なルール設定と運営スタッフによるモニタリングが欠かせません。
本・資料利用の軽視
図書館の本来機能である「読書支援」「専門書の提供」「学習支援」が軽んじられないよう、にぎやかさと学びの両立が求められます。
評価指標の多様性
来館者数や貸出数だけで成功を測ると、本来の価値を見誤ります。滞在時間、満足度、利用者層の広がりなど、多角的な視点で評価する必要があります。
これらの要素が複雑に絡み合うことで、図書館は「静寂」から「共創」へと進化しています。にぎやかな図書館の台頭は、単なる流行ではなく、地域社会の変化に応える“公共空間の再定義”といえるでしょう。
図書館は「まちのリビング」へ
にぎやかな図書館が増えている背景には、図書館が“公共文化施設”から“まちの居場所”へと進化している潮流があります。利用者にとって図書館は、もはや「読むための場所」ではなく、「自分の時間を過ごす場所」へと変化しました。Wi-Fiや電源が整備され、在宅ワーカーや学生が日常的に利用する姿も増えています。
さらに、カフェやワークスペースとの複合化により、世代を超えたコミュニケーションが生まれています。図書館が地域経済や観光と結びつき、まちづくりの中心となるケースも少なくありません。静けさとにぎわいを両立する設計が、これからの図書館の理想形といえるでしょう。
“にぎやかな図書館”がクローズアップ現代で特集されるまでに
2025年10月14日放送のNHK「クローズアップ現代」では、全国で利用者が急増している“にぎやかな図書館”の特集です。テーマは「おしゃべりOK・飲食OK」で地域に活気をもたらす新しい図書館のかたち。番組ではキャスターの桑子真帆さんが岐阜市の人気施設「みんなの森 ぎふメディアコスモス」を訪れ、その独自の仕組みと人の集まる理由に迫りました。
従来の図書館は「静かに本を読む場所」として、会話や飲食を控える空間が当たり前でした。しかしこの番組が伝えたのは、まさにその常識を覆す動きです。おしゃべりや飲食を肯定的に受け入れ、世代を超えて人が集う場に変わったことで、利用者が10倍に増えたという報告も紹介されました。図書館がまちの“にぎわい拠点”として再評価されていることが、全国的な関心を集めています。
番組で映し出されたのは、本を読む人、カフェで語り合う人、子どもを遊ばせる親たちの姿。図書館が学びと交流を兼ね備えた公共空間として、いま大きく進化している現実です。岐阜の事例に限らず、栃木・石川・東京・宮城など全国で“にぎやかな図書館”が増えており、地域の人々にとって身近で温かな居場所となっています。
静けさを守るだけでなく、人と人が出会い、学び、語らう。そんな新しい図書館の姿が全国放送で紹介されるようになったこと自体が、社会が求める公共空間の価値の変化を象徴しています。

“にぎやかさ”が問いかけるもの
図書館がにぎやかになるということは、単なる賑わいではなく、「人が本と人に出会う場所」が再生しているということです。静けさを尊重しつつも、対話や学び合いを許容する新しい価値観が広がっています。静かに読む人も、誰かと語り合う人も、同じ空間に共存できる——そんな公共空間の理想を、図書館が先駆けて実現しているのです。
これからの図書館は、本棚の数ではなく、人がどれだけ心地よく過ごせるかで評価される時代になります。あなたの街の図書館にも、きっと新しい“にぎやかさ”の芽が生まれているはずです。
静けさの中にある“にぎやかさ”を信じて
図書館という場所が、これほどまでに話題になる時代が来るとは思いませんでした。かつて「図書館は静かにするところ」と言われた頃、私たちは本と向き合う時間をひとりで過ごすのが当たり前だと信じていました。しかし今、その価値観が少しずつ変わりつつあります。“にぎやかな図書館”が生まれ、人の声が響く空間に温かさを感じるようになったのは、社会全体が「孤独」と向き合い始めた証なのかもしれません。
図書館が人を呼び戻している理由は、単におしゃれで便利になったからではありません。誰もが安心して過ごせる居場所が、日常の中から減ってしまったからです。カフェでもなく、職場でもなく、家庭でもない——そんな“中間の場所”を求める人たちにとって、図書館の柔らかな開放感はどこか救いのように感じられます。本棚の間をすり抜ける声や、ページをめくる音、子どもの笑い声。それらが重なって生まれる“にぎやかさ”には、誰かと共にいる安心感が宿っているように思うのです。
一方で、静けさを大切にしてきた人たちの気持ちも、決して軽んじてはいけません。静寂の中で言葉と向き合い、自分の心を整理する時間もまた、図書館の本質です。だからこそ本来の図書館のあり方とは、「静けさ」と「にぎやかさ」のどちらか一方ではなく、その両方が共に存在できる場所であるはずです。おしゃべりを許すことは、静けさを壊すことではなく、多様な“静けさのかたち”を増やすことなのだと思います。
番組で紹介された岐阜の「みんなの森 ぎふメディアコスモス」は、その象徴のような存在でした。そこでは、市民一人ひとりが使い方を見つけ、過ごし方を自分で選んでいます。大きな木の下に集うように、本と人が自然につながるその姿は、“図書館は建物ではなく、文化そのもの”であることを思い出させてくれます。人が本を通じて語り合い、偶然の出会いが新しい学びを生む。そんな空間は、技術や効率では作れません。時間をかけて育まれた「人の温度」があってこそ生まれるものです。
取材や調査を進める中で印象的だったのは、どの地域の職員も「図書館を“好き”になってもらうこと」を一番大事にしていたことです。にぎやかさとは、単に声や音の多さではなく、図書館を愛する人が増えることなのかもしれません。一人の利用者がその場を大切に扱い、誰かに薦める。そうした循環が、施設を支え、まちを支え、文化を支えています。だからこそ、これからの図書館は、建築デザインや設備の美しさだけでなく、“人の関係性”のデザインが問われるようになるでしょう。
ただ、理想と現実のあいだには常に課題があります。人が集まれば、摩擦も生まれます。静かに勉強したい人、子どもを遊ばせたい人、談笑を楽しみたい人。それぞれの目的が違う中で、どうすれば皆が心地よく過ごせるのか。その問いに正解はありません。むしろ、その調整を続けていくこと自体が、現代の図書館の“学び”なのだと思います。
そしてもう一つ見逃せないのは、図書館が“まちの縮図”になっているという点です。地域の多様性、経済格差、世代間の価値観の違い――それらすべてが一つの館内に凝縮されています。静けさを守る人、声をかける人、働く人、遊ぶ人。その全員が「同じ屋根の下」にいられることこそ、図書館という公共空間の奇跡です。まちが抱える課題を映し出す鏡でありながら、解決のきっかけを生み出す場所。図書館が支持されるのは、そこに社会の希望が見えるからではないでしょうか。
これからの時代、図書館は“にぎやかであっていい”。むしろ、そのにぎやかさを通じて、人の孤立を防ぎ、まちをつなぐ力を取り戻していくことが期待されています。けれども、それは声を大きくすることではなく、人の声を聞くことです。一人ひとりの声に耳を傾け、場の空気を育てる。そうして育った“にぎやかさ”には、決して騒がしさではない、優しい調和の音があるはずです。
静かな時間と、にぎやかな時間。その両方を受け止められる図書館が、これからのまちを支える灯りになる。この小さな灯りが、全国のまちに静かに、しかし確かに広がっていくことを願っています。
未来への展望|“にぎやかさ”が導く新しい公共のかたち
図書館の変化を見つめていると、そこに現代社会の希望と課題の両方が見えてきます。人が集まる場所が減り、オンラインが日常になった今だからこそ、実際に顔を合わせて過ごす場所の価値が高まっています。その中心に図書館が戻ってきたことは、偶然ではありません。“にぎやかさ”とは、情報ではなく関係をつなぐ力なのです。
多くの図書館では、子どもが走り回る声を受け入れ、若者がPCを広げ、年配の方が読書会を開いています。それぞれの目的が違っても、同じ空間にいるだけで「社会の一員である」という感覚を取り戻せます。誰もが安心して過ごせる公共空間の象徴として、図書館が再び機能し始めているのです。
また、こうした流れは都市だけでなく地方にも広がりつつあります。人口が減り、商店街が静まる地方都市において、図書館は再生のきっかけになり得ます。カフェを併設したり、地元の農産物を扱うコーナーを設けたりと、地域の産業や文化と結びついた事例も増えています。書物だけでなく“まちの記憶”を扱う拠点としての役割を果たしつつあるのです。
一方で、にぎやかさをどう持続させるかはこれからの課題です。建物をつくることよりも、その後の運営や人の関わり方をどう育てるかが重要になります。利用者が自ら関わり、ボランティアや企画に参加することで、図書館は「使われる場所」から「育てる場所」へと変わっていきます。この“参加の循環”が生まれるとき、にぎやかさは一過性ではなく、地域の文化として根づいていくでしょう。
さらに、デジタル化が進む今こそ、図書館が人と情報をつなぐハブとしての力を発揮できます。オンラインで得られる知識と、対面で生まれる気づき。その両方をつなぐ場が図書館であり、そこにこそ新しい時代の公共性があります。デジタル端末を開きながら、隣の人と本をめくる。そんな光景が自然に広がることこそ、これからの“にぎやかさ”の理想かもしれません。
最終的に、図書館とは人が集まり、人が学び、人が支え合う場所です。その本質は、時代が変わっても変わりません。ただ静かなだけでもなく、ただにぎやかなだけでもない。互いを尊重しながら共に生きる場。そこに、これからの社会が目指すべき姿が映し出されています。
“にぎやかな図書館”の流れは、単なる建築トレンドでも運営手法の流行でもなく、人が人を求める自然な願いの表れです。その願いを受け止めるように、各地の図書館が灯りをともしています。その灯りがいつまでも消えず、次の世代へとつながっていくことを、心から願っています。

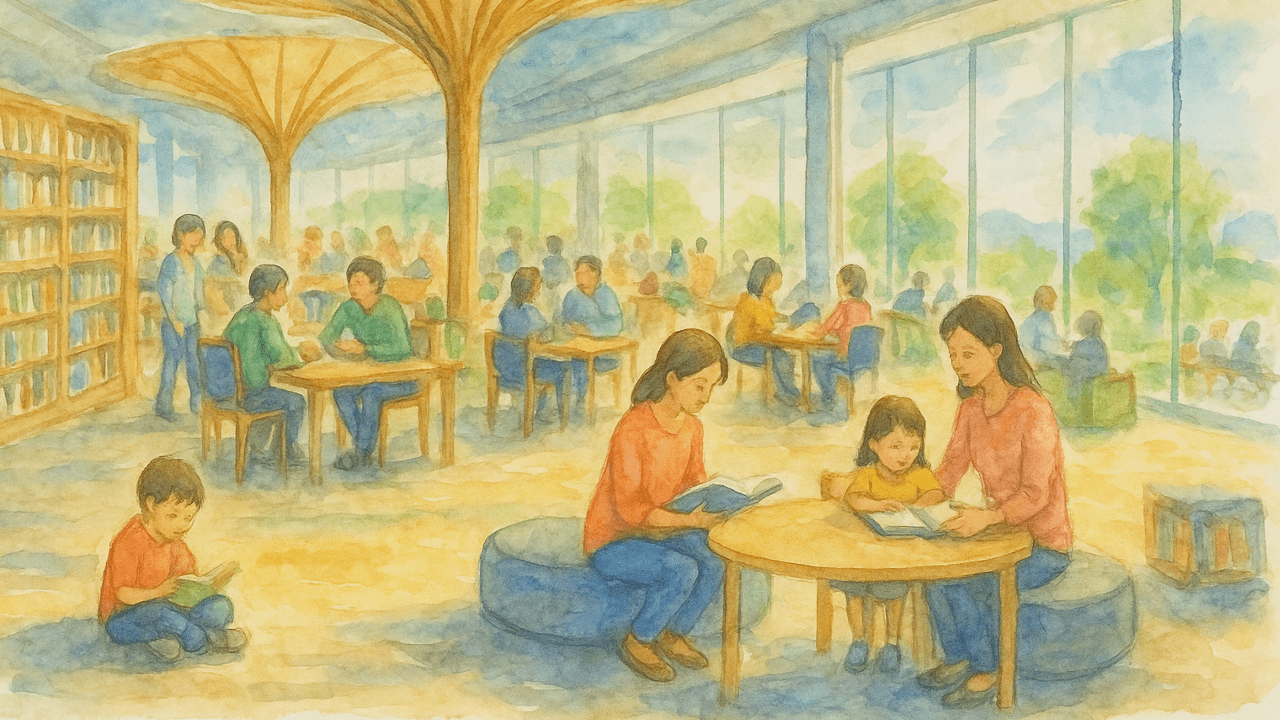
コメント