2025年10月4日(土)18:00~18:30 に放送の『人生の楽園』SPテレビ朝日系 で海と山に抱かれた自然豊かな町長崎県東彼杵(ひがしそのぎ)町が紹介されます。 “楽園の住人”として暮らすのが、齊藤仁さん(59歳)・晶子さん(58歳)のご夫妻です。都会の喧騒を離れ、50歳の節目に東京での仕事を手放し、この町へ移住。2019年には空き家となっていた元旅館を改装し、宿「さいとう宿場」を開業しました。
ご夫妻の物語は、地域を愛し、人をつなぎ、未来を紡ぐ挑戦の連続です。東京で築いたキャリアを下ろしてこの町に身を寄せ、宿づくりと地域活性化に取り組むその姿は、多くの人にとって希望と勇気を投げかけるもの。彼らの日々の歩み、葛藤、そして夢を、この先の章で紐解いていきます。
所在地・行き方
所在地:〒859-3927 長崎県東彼杵郡東彼杵町駄地郷1662−8
電話:0957479723
公式サイト:さいとう宿場
チェックイン:16:00 チェックアウト:10:00
「さいとう宿場」は、長崎県東彼杵町の中心部に位置し、大村湾を望む自然豊かな環境にあります。所在地は長崎県東彼杵郡東彼杵町彼杵宿郷にあり、町の商店街や飲食店にも歩いて行ける便利な立地です。
車で訪れる場合は、長崎自動車道の東彼杵インターチェンジ から約5分。国道34号線を利用すれば長崎市や佐世保市方面からのアクセスもスムーズです。駐車場は宿泊者専用のスペースがあり、普通車であれば数台分が確保されています。
公共交通機関を利用する場合は、JR大村線の東彼杵駅が最寄り駅です。駅から宿までは徒歩圏内で、電車旅の方でも安心。博多方面や長崎空港から高速バスを利用して「彼杵バス停」で下車すれば、徒歩でアクセス可能です。
東彼杵町のアクセス情報
東彼杵町は長崎県の中央部に位置し、交通の要衝としての役割を果たしています。長崎市からは車で約40分、佐世保市からは約50分で到着可能。どちらの都市からも日帰り観光ができる距離です。
福岡・博多方面から訪れる場合は、九州新幹線の博多駅から長崎新幹線「かもめ」に乗車し、新大村駅でJR大村線に乗り換えるルートが便利です。所要時間はおよそ1時間40分ほど。
空路を利用する場合は、長崎空港から車で約20分とアクセス良好。空港から東彼杵町へ直行するバス路線もあり、国内外からの旅行者にとっても訪れやすい場所です。
鉄道・高速道路・空港の三拍子が揃ったアクセス環境の良さは、移住先としての魅力でもあり、観光客にとっても滞在しやすさを感じられるポイントといえるでしょう。
周辺観光スポットと楽しみ方
東彼杵町の魅力は、何といっても大村湾の自然と絶景です。波の穏やかな内海に沈む夕日は、訪れる人の心を癒やします。大村湾沿いにはサイクリングロードや散策コースが整備されており、海風を感じながらのんびりとした時間を楽しめます。
また、町の特産品として知られるのが、そのぎ茶。全国茶品評会で農林水産大臣賞を受賞した実績を持つ名品で、爽やかな香りとまろやかな甘みが特徴です。茶畑の見学や茶摘み体験ができる施設もあり、旅の思い出として人気です。
周辺観光では、山間に広がる温泉地や、地元ならではのグルメが楽しめる食堂もおすすめ。海の幸を味わえる料理や、田園風景を望むカフェもあり、観光と食の両方を満喫できます。春には桜並木、夏には花火大会、秋には紅葉、冬には澄んだ星空と、四季折々の魅力を体験できるのも東彼杵町ならではの楽しみです。
宿泊施設(おすすめ4選)
東彼杵町と周辺地域を訪れる際、旅の目的に合わせて選べる宿が揃っています。ここでは「さいとう宿場」を含めた4つのおすすめ宿を紹介します。
さいとう宿場
移住した齊藤ご夫妻が、空き家だった元旅館を改装して2019年に開業した宿。町ぐるみでのおもてなしが魅力で、地域交流を楽しみながら“暮らすように泊まる”体験ができます。移住を考える方や、地元の空気に触れたい旅行者におすすめです。
そのぎ茶温泉 里山の湯宿 つわぶきの花
山あいに佇む離れ形式の客室で、豊かな自然と温泉を楽しめる隠れ宿。静かにゆったり過ごしたい大人の滞在に最適です。
住所:〒859-3933 長崎県東彼杵郡東彼杵町一ツ石郷字杉ノ尾981
電話番号:0957-47-0744
公式サイト:sonogicha-onsen.com
御慶 緑茶乃宿(ごけ りょくちゃのやど)
千綿駅から車で約3分の好立地で、観光にもビジネスにも便利な宿。お茶の里らしい風情を感じながら滞在できます。
住所:〒859-3921 長崎県東彼杵郡東彼杵町千綿宿郷21-1
電話番号:090-3950-7087
instagram:御慶緑茶乃宿
マツケンの宿
波佐見町にある素泊まりスタイルの宿。シンプルでリーズナブルな宿泊を希望する旅行者に適し、周辺の温浴施設や食事処とあわせて利用すると便利です。
住所:〒859-3725 長崎県東彼杵郡波佐見町長野郷563-2
電話番号:0956-85-7747
公式サイト:matsukennoyado.com
旅行スタイルに合わせて、地域交流を楽しむならさいとう宿場、静かに癒やされたいならつわぶきの花、アクセス重視なら御慶 緑茶乃宿、気軽な素泊まりならマツケンの宿といった選び方ができます。
二人のプロフィールと歩み
大阪出身の齊藤仁さんは、東京で店舗や博物館の企画・施工を担う会社に勤務し、大規模プロジェクトの責任者を務めてきました。チームをまとめ、数多くの現場を手掛けてきた経験は「人と人をつなぐ力」として、のちの宿運営にも生きています。
一方、東京出身の晶子さんは外資系IT企業などで活躍。グローバルな視点と、組織で培った調整力は、宿を切り盛りする際の大きな支えとなりました。
二人に共通していたのは「50歳になったら会社勤めを終えて田舎で暮らす」という夢でした。都会でのキャリアを積み重ねつつも、いつかは自然豊かな土地で、人とのつながりを大切にする生活を送りたいと願い続けていたのです。そしてその節目の2016年、夫婦揃って早期退職を決断し、新しい人生への一歩を踏み出しました。
宿を始めたきっかけ
移住先を探して四国・九州・沖縄を巡る中で出会ったのが、海も山もあり、人も温かい長崎県東彼杵町でした。移住後、仁さんは「地域おこし協力隊」に参加し、町の活性化に携わります。その活動の中で明らかになったのは「町に宿泊施設がほとんどない」という課題でした。観光客や移住希望者が訪れても、気軽に滞在できる場所が不足していたのです。
そこで仁さんは、空き家となっていた元旅館の建物を借り受け、自らの経験を活かして改装。2019年に「さいとう宿場」として再生させました。かつて培った建築・企画のノウハウ、そして夫婦二人三脚で進めた準備が、この宿の礎になっています。
「ここは自然豊かで便利な田舎。この宿を町ぐるみで迎え入れる場所にしたい」と語るご夫妻の思いは、地域にとっても大きな財産となり、訪れる人々にとっては温かな居場所となっています。
二人の今後の夢と挑戦
さいとう宿場を開業して数年、ご夫妻はただ宿を営むだけではなく、町全体の未来を見据えています。まず大きな目標として掲げているのは、宿を通じた地域の活性化です。東彼杵町に来た人々が「また訪れたい」と思えるように、宿を拠点に観光や地元の魅力を発信し続けたいと考えています。
また、ご夫妻は地域住民と連携したおもてなしにも力を入れています。宿で提供する食材を地元農家から仕入れたり、町の人を案内役として紹介することで「宿に泊まる=町全体とつながる」仕組みを少しずつ形にしています。
さらに、移住希望者への発信や体験提供も目標のひとつです。実際に宿を訪れた人が田舎暮らしのリアルを体験し、将来の移住につなげられるような取り組みを強化したいと考えています。ご夫妻の挑戦は、宿という枠を超えて町全体を輝かせるものへと広がりつつあります。
番組の見どころと案内人
ご夫妻の物語は、テレビ朝日系『人生の楽園』で紹介されました。番組では、移住を決断した背景と、宿づくりにかけた思いが丁寧に描かれています。空き家だった元旅館を再生し、新しい価値を生み出した取り組みは、多くの視聴者に感動を与えました。
特に印象的なのは、ご夫妻が語った「ここは自然豊かで便利な田舎。この宿を町ぐるみで迎え入れる場所にしたい」という言葉です。都会のキャリアを手放し、新しい土地で人と人をつなぐ役割を担おうとする真摯な姿勢が番組を通して伝わりました。
番組の見どころは、宿そのものだけでなく、町との関わりや人々との交流、そして田舎暮らしの希望と現実が交差するドラマにあります。視聴者は、移住や地域活性化に関心を持つきっかけを得られるでしょう。
東彼杵町で生まれる“人と人をつなぐ宿”
齊藤仁さん・晶子さんご夫妻の物語は、都会での安定したキャリアを手放し、思い切って新しい暮らしを始める勇気を教えてくれます。50歳という節目に夢を実現させた姿からは、「人生の後半をどう生きるか」を考えるヒントを多く受け取ることができます。
田舎暮らしを志す人にとって、ご夫妻の歩みは具体的な参考になるでしょう。移住先を何度も巡り、条件を整理しながら自分たちに合う土地を見つけたプロセス。地域おこし協力隊での活動を通じて課題を把握し、その解決策として宿を立ち上げた行動力。これらは、移住を成功させるための大切なステップといえます。
また、「さいとう宿場」は単なる宿泊施設ではなく、地域そのものを感じてもらう場所として機能しています。地元の食材や人とのつながりを通して、訪れる人に町全体のおもてなしを体験してもらうという発想は、これからの宿の在り方を示すモデルケースでもあります。
東彼杵町という豊かな自然と温かな人々に囲まれた土地で、ご夫妻が描く“人と人をつなぐ宿”。その挑戦は、地域の未来を照らし、訪れる人の心にも新しい気づきを与えてくれる存在になっています。
東彼杵町で生まれた宿の灯りと人生の豊かさ
東彼杵町の「さいとう宿場」を取材して強く感じたのは、ここが単なる宿泊施設ではないということです。都会のホテルのように設備やサービスの豪華さを競うのではなく、むしろ人と人との距離を縮め、土地の空気に包まれながら滞在できる場として機能している点にこそ価値があるといえます。
齊藤仁さん・晶子さんご夫妻が歩んできた道のりは、多くの人にとって憧れであると同時に、現実的な移住・起業のモデルケースでもあります。50歳という節目に「田舎で暮らす」という夢を叶えるために、二人で決断し、具体的に行動し続けた結果が、現在の「さいとう宿場」として結実しています。都会での安定したキャリアを手放す決断は容易なことではありません。しかし、お二人は不安よりも「これからの人生をどう豊かにするか」を優先したのです。その選択の潔さに、私は大きな学びを得ました。
「便利な田舎」という言葉の奥にあるもの
ご夫妻が東彼杵町を選んだ理由のひとつに「自然豊かで便利な田舎」という表現がありました。この言葉には、地方暮らしを夢見る人にとって重要なヒントが含まれています。田舎に移住したいと考えるとき、自然や人の温かさといった魅力はすぐに目に入りますが、生活の利便性は見落としがちなポイントです。東彼杵町は高速道路や鉄道、新幹線、そして空港へのアクセスが良く、都市部からの移動も容易です。さらに、日常生活に必要な商業施設や医療機関も整っています。そのバランスが、移住生活を「特別な非日常」ではなく「持続可能な日常」として根づかせる大きな要素になっているのです。
「宿を開く」という挑戦が持つ意味
移住後に直面した「町に宿泊施設がない」という課題に対して、お二人が選んだのは「宿を開く」という挑戦でした。空き家の元旅館を自ら改装し、人々が安心して泊まれる場をつくる。その取り組みは単に宿泊施設を提供する以上の意味を持っています。宿は外から来た人を迎え入れる「玄関口」となり、町の顔となります。訪れた人が東彼杵町をどう感じるかは、この宿での体験に大きく左右されるでしょう。だからこそ、ご夫妻は「町ぐるみでおもてなしをする宿」を目指しています。
実際に滞在した人々は、宿での交流を通じて地元の農家や漁師、商店の人々と出会い、町全体の温かさを感じ取ることができます。これは単に観光客を迎えるのではなく、地域の未来を担う人との出会いの場を創り出しているのです。宿を通じて人と人をつなぎ、笑顔をつなぎ、町の未来をつなぐ。その発想が「さいとう宿場」の最大の価値であり、移住先で新たな挑戦をしたご夫妻の生き方を象徴していると感じます。
地域に根づく覚悟と喜び
移住者にとって最も大切なのは「地域に根づく覚悟」ではないでしょうか。外から来た人が新しい風を吹き込むことは確かに地域活性化につながりますが、一方で地域の人々に受け入れられるためには信頼関係を築く努力が欠かせません。仁さんは地域おこし協力隊として活動する中で、町の課題を共有し、一緒に汗をかいてきました。その姿勢があったからこそ、空き家を借りて宿に改装するという挑戦も地域に歓迎され、応援される形で進めることができたのだと思います。
ご夫妻は「移住して終わり」ではなく「移住してからが始まり」だと体現しています。宿の運営は決して楽な仕事ではなく、日々の掃除や食事の準備、予約対応など細やかな気配りが求められます。それでもお二人は「お客さまの笑顔に出会えることが何よりの喜び」と語ります。この言葉には、田舎暮らしのリアルな大変さを超えて、地域に根ざし、人とのつながりを育む暮らしの豊かさが凝縮されているように思います。
東彼杵町という地域の再発見
取材を通じて改めて感じたのは、東彼杵町という地域の可能性です。大村湾の穏やかな海と、緑豊かな山々。その自然の恵みは四季折々の風景として訪れる人を魅了します。そして「そのぎ茶」に代表される特産品は、地域の誇りとして受け継がれています。こうした自然と文化が調和した町に、都会からの移住者が加わり、新しい風を吹き込んでいるのです。
「さいとう宿場」の存在は、町を訪れる人にとって地域の魅力を発見する入り口となり、地域の人々にとっても自分たちの暮らしを見つめ直すきっかけになっているのではないでしょうか。外から来た視点と地元の力が合わさることで、東彼杵町はこれからも新しい価値を生み出していくはずです。
移住と宿づくりに挑戦する人生の豊かさ
筆者が最も心を打たれたのは、ご夫妻の人生観です。「都会での安定」ではなく「新しい挑戦」を選び、その中で地域と共に歩む道を選んだ姿勢は、多くの人に勇気を与えるでしょう。移住は決して簡単な道ではありませんが、人生を豊かにする可能性を秘めています。そして宿づくりという挑戦は、人と人とをつなぐ場を生み出し、自分たちの生き方を社会に還元する営みでもあります。
これから先も「さいとう宿場」を拠点に、ご夫妻は人と地域を結びつける役割を果たしていくことでしょう。その姿は、移住やセカンドライフを考える人にとって大きな指針となり、また東彼杵町の未来を照らす灯りとなるはずです。
「人生の楽園」という番組名が示すように、楽園はどこか遠い場所にあるのではなく、自らの決断と行動によって築き上げるものなのだと、ご夫妻の物語を通して感じました。東彼杵町で生まれた一軒の宿は、これからも人と人を結び、町と町を結び、未来へと続く物語を紡いでいくことでしょう。
東彼杵町に宿が生まれた意味とこれからの物語
長崎県東彼杵町に生まれた「さいとう宿場」は、単なる宿泊施設ではなく、地域と訪れる人々をつなぐ結節点です。東京から移住した齊藤ご夫妻が、空き家だった元旅館を自ら改装して生まれ変わらせた背景には、町に「泊まる場所がない」という課題がありました。その課題を自分ごととして受け止め、一歩踏み出した姿は、多くの人の心を打ちます。
ここで注目すべきは、ご夫妻が歩んできた人生経験の活かし方です。仁さんは長年にわたり、博物館や店舗の施工・企画に携わってきました。その経験が宿の改装にも活かされ、落ち着きのある空間へと生まれ変わったのです。また晶子さんがIT企業で培った情報発信力やコミュニケーション力は、宿の運営に欠かせないものとなっています。二人のキャリアが自然に組み合わさり、地域にとっても訪れる人にとっても価値ある拠点が形づくられているのです。
訪れる人に与える体験価値
「さいとう宿場」に泊まる魅力は、建物やサービスの良さだけではありません。最大の特長は、町全体が宿の一部のように感じられることです。夕暮れ時に散歩をすれば地元の人に声をかけられ、食事処では「どこから来たの?」と気さくに話しかけられる。宿を拠点に、自然に地域とのつながりが生まれるのです。
旅先で人との出会いが心に残る体験となるのは、こうした温かさがあるからこそ。大村湾に沈む夕日を見ながら、都会では得られないゆったりとした時間を味わう。朝にはそのぎ茶の爽やかな香りを楽しみながら散策する。こうした一つひとつの体験が、宿を訪れる人に深い満足感を与えてくれます。
移住を考える人への学び
この物語は、田舎暮らしを検討する人にとっても大きな示唆を含んでいます。ご夫妻は「50歳になったら会社勤めをやめる」と早くから目標を持ち、その準備を着実に進めてきました。地方に移住する際に必要なのは、理想を描くだけでなく、生活の条件を冷静に見極めること。交通の利便性、医療機関や買い物のしやすさなど、現実的な要素を重視した選択が、ご夫妻の暮らしを安定させています。
また、地域おこし協力隊での活動を通じて、まずは「地域の中に入って役立つことをする」という姿勢を持ったことも成功の要因です。いきなり移住して何かを始めるのではなく、地域に寄り添いながら課題を共有し、その解決に力を注ぐ。その積み重ねが信頼関係を築き、宿づくりの応援にもつながったのです。
地域に広がる効果
「さいとう宿場」の誕生は、東彼杵町全体にもプラスの効果を生んでいます。宿があることで観光客が滞在しやすくなり、周辺の飲食店や土産物店、観光スポットへの回遊が生まれます。地域全体の経済循環にとっても宿は重要な役割を果たしています。
さらに、訪れた人が地域の魅力をSNSなどで発信することで、町の知名度も上がります。小さな町でも、一人ひとりの発信が積み重なることで「行ってみたい場所」として注目されるのです。ご夫妻の宿は、町にとってまさに「未来をつなぐ扉」といえるでしょう。
これからの挑戦
今後、ご夫妻は宿を中心に「町全体でもてなす場所」にしていきたいと語っています。そのためには地域住民とのさらなる連携が欠かせません。食材の提供や観光案内、体験プログラムの共同企画など、地域の人々と一緒につくる宿の形を模索しています。
また、移住希望者や二拠点生活を考える人に向けて、宿泊とあわせて「暮らし体験」を提供する取り組みも構想中です。実際に町で数日間を過ごすことで、生活のリアルを知り、移住後のギャップを少なくすることができます。こうした試みは、全国の移住促進のモデルにもなり得るものです。
齊藤ご夫妻の物語から学べるのは、「新しい挑戦に遅すぎることはない」ということです。人生の折り返し地点であっても、自分たちの夢を形にする勇気と行動力があれば、暮らしは大きく変わります。東彼杵町の自然と人の温かさに支えられながら、ご夫妻は新しい宿を生み出し、そこから地域と未来をつなぐ物語を紡いでいます。
この地に宿があることで、人と人が出会い、笑顔が生まれ、町が輝きを増していく。その姿は、地方の小さな町が持つ無限の可能性を教えてくれるのです。訪れる人は旅の思い出を胸に、地域の人は誇りを胸に、そしてご夫妻は夢を胸に、それぞれの物語を続けていくことでしょう。

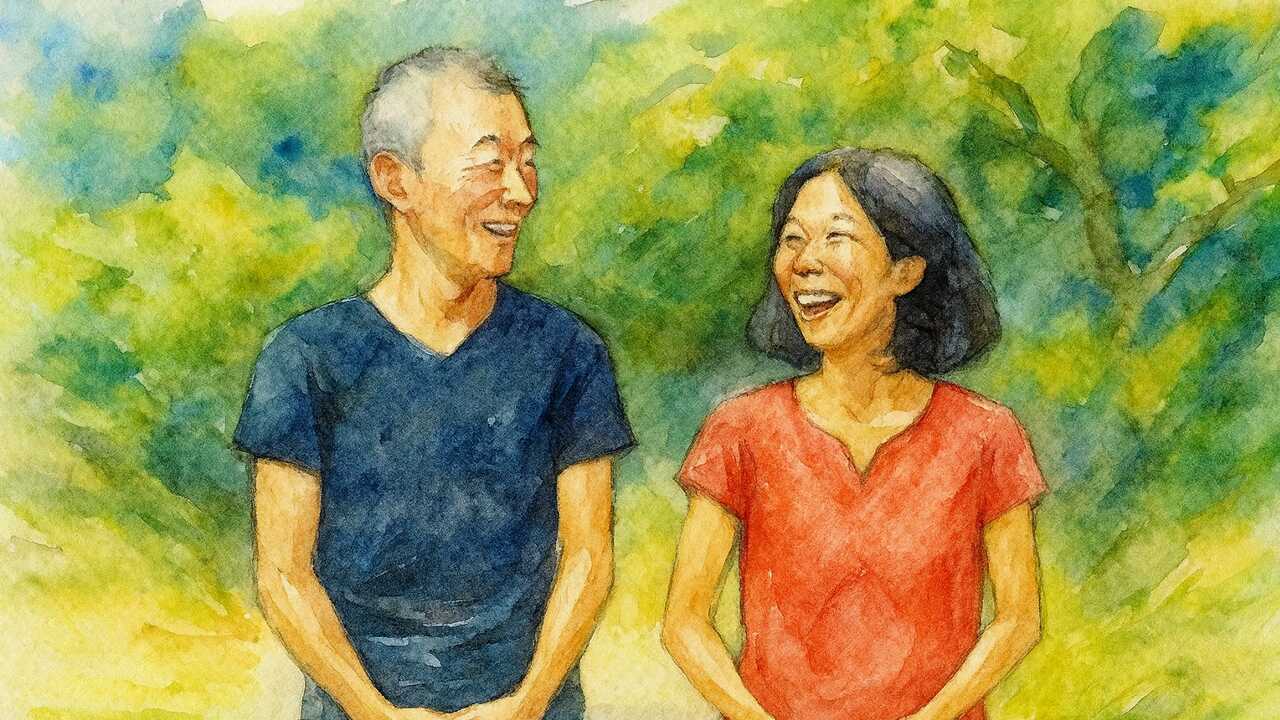
コメント