NHK Eテレの番組「ヴィランの言い分」(2025年9月20日10:30〜・24日水曜日19:25〜放映)では、普段は嫌われがちな現象や病気をあえて悪役に見立て、その立場から語らせるユニークな構成で放送しています。今回取り上げられたテーマは「乗り物酔い」です。ドライブや遠足を楽しみにしていても、気分が悪くなり台無しになった経験は多くの人が持っています。なぜ酔うのか、どうすれば防げるのか、その答えを探る研究は私たちの日常生活だけでなく、宇宙開発やVR技術にも応用されています。このコンテンツでは、番組の趣旨を紹介しながら、乗り物酔いの仕組みや最新研究、対策までをわかりやすく整理して解説します。誰もが一度は悩まされたことのある不快な症状を正しく理解し、克服するヒントを見つけていただければと思います。
乗り物酔いとは?症状と日常への影響
乗り物酔いは、車やバス、船や飛行機に乗ったときに発生する体の不調をまとめた呼び方です。主な症状としては吐き気、頭痛、冷や汗、顔色の悪化、強い眠気や倦怠感などが挙げられます。多くの場合、乗っている途中から違和感が生じ、進行するにつれて食欲がなくなり、嘔吐に至ることもあります。
特に子どもは感覚のバランスを保つ機能がまだ発達段階にあるため酔いやすく、また高齢者も体の機能が弱まっていることで症状が出やすいとされます。旅行や遠足を楽しみにしていたのに、バスの中で気分が悪くなって思い出が苦いものになったという経験は珍しくありません。家庭や学校行事だけでなく、通勤や通学の電車やバスで毎日のように悩まされる人もいます。こうした症状は肉体的な不快さだけでなく、精神的なストレスや外出の不安にもつながるため、日常生活への影響は決して小さくありません。
なぜ酔うのか?メカニズムの科学
乗り物酔いが起こる原因は、脳が受け取る情報の矛盾にあります。私たちの体は、目から入る景色の情報、内耳にある三半規管が感知する体の動き、そして筋肉や関節から伝わる体勢の情報を組み合わせて、バランスを取っています。ところが乗り物に乗ると、この情報が一致しないことがあります。
例えばバスで座って本を読んでいるとき、目は「体は静止している」と感じます。しかし実際には車体は加速や減速、カーブの連続で揺れ動いており、三半規管は「大きく動いている」と判断します。この食い違いが脳を混乱させ、処理しきれなくなった結果、嘔吐中枢と呼ばれる部分に信号が送られ、吐き気や頭痛といった症状が出ます。
つまり、乗り物酔いは体が壊れたわけではなく、情報のズレによる脳のパニック反応です。この仕組みを理解することで、視覚を外の景色に合わせるなど対策を立てやすくなります。科学的な背景を知ることは、日常の工夫にも直結します。
三半規管と平衡感覚の仕組み
内耳には前庭という平衡の中枢があり三半規管と耳石器が働きを分担します。三半規管は三本の管が互いに直角に配置されて頭の回転加速度を感じます。管の中の内リンパ液が動き感覚毛が曲がることで動きを電気信号に変えます。耳石器は卵形嚢と球形嚢からなり重力と直線加速度を感じます。炭酸カルシウムの小さな粒が動き感覚毛を刺激して体の傾きや加減速を知らせます。これらの信号は前庭神経を通って脳幹の前庭神経核に集まり視覚や体性感覚と統合されます。筋肉や関節から届く体勢情報と目で見た景色の動きと内耳が感じた加速度が一致すると姿勢と眼球運動が安定します。視線を保つ仕組みは前庭動眼反射が担い頭が動いても目を反対方向に素早く動かして像を網膜の中央に保ちます。車内で周囲が揺れているのに視線を近距離の本や画面に固定すると視覚情報と内耳情報がずれて統合が難しくなります。そのずれが広がるほど脳は状況判断に負荷がかかり不快感につながります。平衡感覚は視覚と体性感覚と協調して働くため一つでも大きく乱れると全体の調和が崩れます。乗り物内では視覚と内耳の情報が一致しにくいのでずれを小さくする工夫が重要になります。
脳の持つ“酔い克服”の仕組みとは?
人の脳は環境の反復に慣れる性質を持ち前庭の入力に対しても適応します。繰り返し同じ動きを経験すると前庭動眼反射の利得が調整され視線のぶれが減ります。船やバスの揺れに乗客がしだいに慣れて数時間後に気分が落ち着く現象はこの適応の一例です。段階的に負荷を上げるトレーニングは症状の軽減に役立ちます。短時間で終える乗車を増やして揺れの種類を少しずつ広げて視線を遠くに置く練習を行い首を安定させて姿勢の微調整を学びます。バランス訓練や視線安定化練習は前庭系と眼球運動の協調を整えます。ゆっくり頭を回しながら一点を見続ける基本練習は日常でも取り入れやすい方法です。十分な休息と水分補給は自律神経の安定に寄与します。過度の疲労や睡眠不足は前庭入力への耐性を下げます。脳は入力と出力の差を学習し誤差を減らす方向に調整します。この働きがいわばリセットに相当し新しい環境の基準に合わせて感度を最適化します。無理は禁物で悪化する時は刺激を弱めて落ち着くまで静かな姿勢を保ちます。適応は連続性が大切で少しずつ積み上げるほど効果が持続します。
乗り物酔いの克服法(一般編)
座席の選び方は最初の対策になります。車は前席で進行方向に向き頭と背中をシートに預けます。バスは前方の窓側で車軸に近い席が揺れが小さく感じやすいです。鉄道は進行方向の窓側で台車上を避け中央寄りに座ります。飛行機は主翼付近が上下動が少なく安定します。船は中央の下層が上下動が小さいです。視線は遠くの固定物に置きます。地平線や遠方の建物を見て内耳の情報と視覚の動きを近づけます。近距離の本や画面は控えます。首を安定させ背もたれに頭を軽く当てます。換気を行い新鮮な空気を取り入れます。強いにおいは避けます。前日は十分に睡眠を取り当日は空腹すぎず満腹すぎない軽食にします。脂っこい食事や過度な糖分は避け水を少量ずつ取り脱水を防ぎます。出発前にルートと休憩計画を立てこまめに体勢を変えて軽いストレッチをします。運転者は急加速急減速急ハンドルを避けて一定のリズムで走行します。子どもは目線が高いほど外の景色が見やすくなります。会話や音楽で注意を分散し不安を減らします。気分が悪くなったら早めに休憩し風に当たり楽な姿勢で深く呼吸します。吐き気が強い時は頭を動かさず視線を遠くに置きます。これらの基本を組み合わせるとずれが小さくなり症状が和らぎます。
薬と食べ物での対策
薬は事前投与が基本になります。市販の酔い止めは抗ヒスタミン薬を中心に配合され乗車の三十分から一時間前の服用が推奨されます。眠気や口の渇きが出ることがあるので重要な作業や飲酒と併用しないようにします。年齢や体重に合わせた用量を守ります。小児は対象年齢と用量の確認が必須です。シロップやチュアブルは服用しやすいですが保護者が管理します。持病がある人は事前に医師や薬剤師に相談します。一部の薬は緑内障や前立腺肥大などで注意が必要です。妊娠中や授乳中は自己判断での服用を避けます。必要性と安全性を専門家と確認します。食べ物ではショウガが吐き気の軽減に役立つ知見があり飴や温かい飲み物が取り入れやすいです。梅干しやレモンは唾液分泌を促して口の不快感を和らげます。強い香辛料や脂質の多い食事は控えめにします。こまめな水分補給は脱水を防ぎます。手首の内側の圧迫バンドは簡便な方法として用いられます。効果には個人差があるので感覚に合うものを選びます。薬と生活対策を組み合わせ準備と早めの対応を徹底すると症状の立ち上がりを抑えられます。無理に我慢せず休息を取り必要に応じて医療機関で相談します。
宇宙酔いとその研究
宇宙飛行士が経験する宇宙酔いは重力がほとんど働かない環境で前庭系の基準が一気に変わることで起こります。内耳の耳石器は重力の向きを手掛かりに体の傾きや直線加速度を感じます。無重量に入るとこの手掛かりが失われ視覚や体性感覚との統合が乱れます。船酔いや車酔いと似た吐き気や頭重感や眠気が出やすくなります。発症は入室後の初期に多く現れます。そして多くの隊員は数日の適応で症状が和らぎます。対策の基本は急な頭部運動を控えることです。視線を安定させ作業姿勢をゆっくり変えます。作業計画を初期は軽めにする運用は有効です。地上では視線安定化の訓練やバランス練習やパラボリックフライトでの前庭負荷への慣れが用いられます。薬物では吐き気や前庭過敏を抑える薬が使われます。服用の可否やタイミングは医療チームが決めます。船内設計では参照できる固定物を視界に置き姿勢の基準をつくります。手すりの配置や作業手順の単純化は過度の体動を減らします。研究面では前庭入力と視覚刺激の組み合わせを系統的に変え脳がどの条件で混乱するかを計測します。眼球運動の解析や生体センサーでの自律神経指標は早期兆候の検出に役立ちます。宇宙での適応の知見は長期滞在の健康管理や帰還後のリハビリに活かされます。そして乗り物酔いの理解を深める基礎として日常の対策にも還元されます。
VR酔いの正体と最新対策
VR酔いは視覚が示す移動や回転の情報に対して内耳が感じる加速度が伴わないことで起こる感覚の食い違いが主因です。映像の自己運動感が強いほど前庭系との矛盾が大きくなります。ゲーム業界ではこの矛盾を小さくする設計が進みます。移動はスティックの連続移動よりテレポートや段階的なスナップターンを採用します。視界の縁を暗くするビネットで周辺視を落ち着かせます。頭の向きとは無関係に揺れる過剰なカメラ演出は避けます。視線のよりどころになる固定フレームや仮想コックピットを画面内に置きます。フレームレートは十分に高く保ち遅延は可能な限り短くします。描画負荷を下げる工夫や時間方向の補間は安定に寄与します。ユーザー設定で視野角や移動方式や回転角を選べるようにします。装着時の瞳孔間距離やレンズ位置を正しく合わせます。発汗や顔面圧で不快感が増すため装着感の調整と短時間の休憩が重要です。体験の始めは滞在時間を短くし徐々に延ばします。開発では前庭研究の知見を取り入れます。例えば安定した地平線の提示や頭部運動に対する視覚遅延の最小化や急加速の抑制などです。ユーザーテストでは吐き気やめまいの主観指標だけでなく眼球運動と頭部運動の同期も評価します。これらを積み重ねることで没入感と快適性の両立が進みます。
「ヴィラン」としての乗り物酔いの言い分
この番組では乗り物酔いが自ら弁明する設定で語られます。悪気はないと語る語り口は被害者である視聴者の気持ちに寄り添いつつ原因の本質に近づく工夫になります。視覚と三半規管の情報がずれると脳が混乱するという難しい理屈も擬人化の台詞にのせると直感的に理解できます。急カーブが続くとつい指令を出してしまうという表現は嘔吐中枢への信号という生理学の説明をやわらかく言い換えたものです。ユーモアは不快な体験への拒否感を和らげます。そして視聴者は笑いながら自分の行動を振り返れます。近くを見続けるより遠くの景色に視線を置くと楽になるといった実践的なヒントも物語の流れで自然に腑に落ちます。悪役の言い分を聞くという構図は責めるだけでなく理由を知り対処を学ぶ態度を促します。身近な不快現象を面白く伝えることで学びのハードルは下がります。知ることは恐れを減らします。減った恐れは行動の工夫へつながります。そして工夫は症状の軽減に結びつきます。番組の狙いはここにあります。
「ヴィランの言い分」とは?番組の特徴と趣旨
「ヴィランの言い分」は、身近でありながら人々を困らせる存在を“ヴィラン=悪役”として登場させ、その立場から「言い分」を語らせる教育番組です。難しい科学や医学の内容を専門用語だけで説明すると理解が追いつかないこともありますが、この番組では擬人化やユーモラスな表現を取り入れることで、子どもから大人まで楽しみながら学べるようになっています。
今回のテーマである「乗り物酔い」も、あたかも悪役が「悪気はないんです」と弁解するように描かれています。視覚と三半規管の感覚のずれが脳を混乱させ、結果として不快な症状を起こすメカニズムを、ドラマ仕立てで紹介してくれるため、難しい生理学の話も自然と頭に入ります。科学を身近に感じさせ、普段なら敬遠される内容を親しみやすく伝えることこそ、この番組の大きな特徴といえます。
出演者紹介
司会の八嶋智人さんは複雑な内容を短い言葉に置き換え要点を素早く整理します。登場人物の会話を受けて視聴者の疑問をその場で言語化します。テンポのよい進行で場を温めつつ専門的な説明に橋を架けます。みなみかわさんは体験談や素朴な疑問を差し込みます。難しさに寄り過ぎないバランスをつくります。思わず笑ってしまう一言が緊張をほどきます。川口由梨香さんは現場の声を丁寧に拾います。視覚と前庭のずれを体験として示すリポートは理解の助けになります。小倉優子さんは生活者の視点で具体的な困りごとを挙げます。家族や子どもへの配慮という観点が加わります。ふくらPさんは試す姿勢で検証のきっかけを示します。操作や設定の工夫に注目し実践的な気づきを引き出します。語りの武内駿輔さんは要点を落ち着いた声で繋ぎます。科学用語の登場場面でも耳にすっと入る運びをつくります。全員の役割が重なりすぎずに補い合うことで学びと娯楽の両立が生まれます。そして乗り物酔いという身近なテーマが一歩近づきます。
乗り物酔いと暮らしの工夫
乗り物酔いは一度起こるとその日の予定が大きく乱れることがあります。そのため日常生活の中で少しずつ工夫を積み重ねることが予防につながります。家族旅行では出発前に軽めの食事をとり車内では換気を心掛けます。座席は進行方向に向きできるだけ揺れの少ない場所を選びます。途中で休憩をはさみ外気に触れると体調が安定しやすくなります。子どもは大人より酔いやすいため座席位置を前にして外の景色が見えるようにします。ゲームや読書は控え声をかけたり歌を歌ったりして気をそらすことも効果的です。酔いが出たときは無理をさせず静かに休ませ水分を少量ずつ与えます。通勤や通学では時間に余裕を持ち混雑を避けることが望ましいです。座れないときは体を安定させ視線を前に向けると負担が軽くなります。スマートフォンの長時間利用は避ける方がよいです。高齢者は体の調整力が低下しやすいため事前の休養と水分補給が大切です。持病の薬との飲み合わせにも注意し必要があれば医師に相談します。心疾患やめまいの既往がある人は特に慎重な対応が必要です。暮らしの中でできる小さな工夫は症状を軽減し不安を減らす助けとなります。そして安心して外出を楽しむための支えになります。
最新テクノロジーで変わる酔い対策
近年はテクノロジーを利用した乗り物酔い対策の研究が進んでいます。ウェアラブル機器には心拍や皮膚電位や体の傾きを測定する機能が備わり酔いの兆候を早期に捉えることが可能になっています。異常な変化を検知すると振動や通知で休息を促し症状が重くなる前に対応できます。自動運転車の普及に向けては新しい課題もあります。乗客は運転に集中せず読書や作業をする時間が増えるため視覚と前庭のずれが強まりやすくなります。そのため車両設計では座席の位置や画面の配置や視界に基準となる目印を取り入れる試みが進められています。医療とテクノロジーの連携も注目されています。バーチャル空間を用いた平衡感覚の訓練や前庭リハビリは慢性的なめまいや酔いに効果が期待されています。さらに人工知能を活用して体の反応を解析し個々の耐性に合わせた予測とアドバイスを行う研究も進みます。従来の生活の工夫に加えてこうした技術が広がれば安全で快適な移動が実現しやすくなります。新しい社会では酔いを避けることが当たり前の環境が整う可能性があります。そしてそれは子どもから高齢者まで誰にとっても恩恵となります。
まとめ|不快な現象を未来に活かす
乗り物酔いは誰にとっても身近で避けたい現象ですがその仕組みを理解すれば恐れるだけでなく活用できる分野が見えてきます。視覚と前庭の矛盾が脳を混乱させることが原因であると知ることで私たちは対策を立てやすくなります。座席の選び方や視線の置き方や体調管理など日常の工夫は効果を生みます。そして研究は宇宙やVRといった新しい領域で進められています。宇宙酔いの克服は宇宙飛行士の健康を守り未来の探査を支えます。VR酔いの対策はデジタル社会の快適さを広げます。さらに医療や自動運転車の分野でも応用が進みます。不快な現象を単なる困りごとで終わらせず理解し克服する姿勢が未来を切り開きます。番組が示したように乗り物酔いにも言い分があり悪意ではなく体の仕組みの結果であると捉えると気持ちも軽くなります。正しい知識と工夫で症状を和らげることができれば移動の不安は減り安心と快適が広がります。これからの社会では酔いの研究成果が人々の生活を支える基盤となりより自由で安全な移動を実現する力となります。
「酔い」という名の悪役が教えてくれること
乗り物酔いという現象を悪役になぞらえて語る番組を見て、私は一つの大きな気づきを得ました。悪役というと怖くて排除したい存在に思われがちですが、この番組が描き出したのは、実は私たちの体にとって必要なサインを発するメッセンジャーでもあるということです。吐き気や頭痛は歓迎できるものではありませんが、その背景には脳が必死に情報を整理しようとする姿が隠れています。つまり酔いとは不具合ではなく、むしろ命を守るための過剰反応であり、その正体を知ることで安心につながるのです。
ここで思い出すのは宇宙飛行士の「宇宙酔い」です。地上では想像もできない無重力空間で人間の体は大きな混乱に直面します。前庭系が基準を失い、視覚と体感覚の間にずれが生まれるのです。最初の数日間は吐き気に苦しむ飛行士も多いと聞きますが、不思議なことに時間とともに体は慣れていきます。人間の適応力の強さには驚かされます。これは単に生理現象を克服する話ではなく、未知の環境に対応していく人類の可能性を象徴しているように感じます。乗り物酔いの研究が宇宙探査の支えになるのだと考えると、不快な体験にも大いなる価値が隠れていることに気づかされます。
また現代社会ではVR酔いが新たな課題として注目されています。子どものころ本を読みながらバスで気分が悪くなった経験と、VRゴーグルをかけて立っていられなくなる感覚は、一見別のようでいて根は同じです。視覚と内耳が伝える信号がずれれば、脳は混乱します。こう考えると酔いは時代を超えて普遍的な現象です。古代の船旅でも近未来のデジタル空間でも、悪役の姿は変わらず登場します。違うのは、それをどう受け止めるかです。科学と技術の力で少しずつコントロールできるようになったいま、酔いは単なる敵ではなく、進歩の原動力に変わってきています。
番組の工夫もまた印象的でした。酔いを「悪気はない」と弁明させることで、私たちに笑いと理解を同時に与えてくれました。生理学的な説明だけでは堅苦しくなりがちですが、擬人化された悪役が登場すると子どもでも直感的に仕組みを理解できます。しかも不快な体験が少し軽く見えてくるのです。これは教育番組ならではの巧みな演出です。科学を身近に引き寄せ、日常の困りごとをユーモラスに照らす視点に感心しました。
ここで少し裏話的な視点を加えると、乗り物酔いの研究は実は軍事や航空分野でも長く行われてきました。飛行機の操縦士や潜水艦の乗員は、極度の環境下で平衡感覚の維持が不可欠です。安全な任務遂行のために、研究者たちは地道に実験と訓練方法を積み上げてきました。その成果が私たちの一般的な酔い止め薬や生活の工夫に応用されていると考えると、普段手に取る薬の背後に壮大な歴史があることに気づきます。テレビの30分番組で紹介される背景には、数十年にわたる膨大な研究と試行錯誤が隠れているのです。
さらにグローバルな視点で見ると、乗り物酔いは文化や地域を問わず人類共通の体験です。船で世界を巡った探検家も、蒸気機関車に初めて乗った人も、飛行機旅行が一般化した時代の人々も、同じように酔いと向き合ってきました。これはまるで人類が進歩するたびに現れる通過儀礼のようです。だからこそその対策は各国で工夫され、食文化や医療慣習とも結びつきました。日本では梅干しやショウガが親しまれ、欧米ではミントやジンジャービスケットが活用されました。異なる文化が同じ現象に対して独自の解決策を見つけ出してきたことは、乗り物酔いが人間にとって普遍的な課題であることの証明です。
宇宙的な観点に立てば、酔いは人間が地球を超えて活動する際の大きな壁です。火星探査や月面基地の計画が現実味を帯びるなかで、長期間の宇宙飛行における平衡感覚の維持は避けて通れません。もしも人類が太陽系を旅する未来が来るとしたら、その最初の一歩を阻むのは巨大な隕石やエネルギー不足ではなく、意外にも「酔い」なのかもしれません。そう考えると滑稽にも思えますが、それだけに克服する意義は大きいのです。悪役が立ちはだかるからこそ物語は進みます。酔いを乗り越えることは人類の物語を次の章へ進める条件なのです。
もちろん日常の範囲でも酔いは決して軽視できません。通勤通学で毎日のように乗り物を利用する人にとっては切実な問題です。子どもの遠足で笑顔を失わせないためにも、高齢者の安全な外出を守るためにも、身近な知識と工夫が欠かせません。番組は科学の話を身近な生活に結びつけて伝えてくれました。大げさな理屈より、すぐ実践できる工夫が人を救うことを改めて教えてくれました。
最後に、私はこの番組に強い応援の気持ちを伝えたいです。科学の番組はとかく難解で堅苦しくなりがちですが、「ヴィランの言い分」は笑いと驚きを交えて誰もが理解できる形に仕立ててくれます。不快で避けたい現象にあえてスポットを当て、悪役の声を聞くという発想は斬新であり、優しささえ感じます。悪役の存在を知り、理由を理解し、工夫を重ねることで日常が少し楽になる。そんな番組作りは教育的でありながら人間味にあふれています。
酔いは嫌われ者ですが、その言い分に耳を傾けることで新しい視点が得られます。そしてその知識は未来の宇宙旅行やデジタル体験を支える力になります。悪役がいるからこそ物語は面白くなり、私たちは成長できるのです。これからも「ヴィランの言い分」が多くの人に気づきを与え、笑顔を届けてくれることを願っています。
酔いの多面性と未来への道しるべ
乗り物酔いをテーマにした番組を振り返ると、あらためて「なぜ人は酔うのか」という根源的な問いに向き合うことの大切さを感じます。検索でも「乗り物酔い 原因」や「酔い止め 方法」といった疑問は常に上位に並びます。これは多くの人が日常で困り、解決策を求めている証拠です。SEO的に見ても、原因と仕組みを明快に説明し、そこから具体的な克服法につなげることが求められます。そして番組が示した「悪役にも言い分がある」という視点は、難しい医学的知識を平易に伝える強力なフレームになっているといえるでしょう。
生活の場でできる工夫
日常生活での対策は「ユーザビリティ」が最も重視されます。読者が知りたいのは専門的な論文の詳細ではなく、すぐに実践できる具体策です。例えば「遠くの景色に視線を合わせる」「前日の睡眠をしっかりとる」「空腹や満腹を避ける」といった方法は、すぐに検索結果からも求められる情報です。また「酔いやすい子どもにどう対応すればいいか」「通勤電車でのスマホ利用は控えた方がいいか」といった具体的な疑問に答えることは、ユーザビリティを高める重要な要素になります。
宇宙酔いとVR酔いの広がり
検索意図を意識すると「宇宙酔い」や「VR酔い」といった関連語も見逃せません。宇宙飛行士が訓練で克服する過程や、VRゲーム開発での改善策は、多くの人が関心を寄せる分野です。これらの情報を取り込むことで、記事全体の網羅性が増し、SEO評価にもつながります。番組でも紹介されたように、酔いの研究は地球規模から宇宙規模へと広がっています。かつてはドライブやバス遠足を楽しむための工夫だった知識が、いまや宇宙探査やデジタル体験の基盤になっていることは驚きです。
ユーモアが生む理解
ここで忘れてはならないのが番組のユーモアです。不快な現象を笑いながら学ぶという体験は、SEOでの直帰率を下げ、滞在時間を伸ばす効果にもつながります。検索でたどり着いた人が「なるほど」と頷くだけでなく「面白かった」と感じてくれることが、記事全体の価値を高めます。酔いという嫌われ者にあえて耳を傾ける構成は、知識を楽しく消化させる強い力を持っています。
未来への布石
最後に強調したいのは「酔いを克服することは未来を広げる」という点です。自動運転車が普及すれば、乗客は車内で読書や仕事をする時間が増えます。そのときに酔いを防ぐ技術は必須です。さらに宇宙開発が進めば、火星旅行や月面基地での生活においても同じ課題に直面します。つまり「乗り物酔い 対策」の研究は人類の未来そのものに直結しているのです。
番組がユーモラスに描いた「悪役の言い分」を思い出せば不快な体験すら未来を支える力へと変わっていくのではないでしょうか。
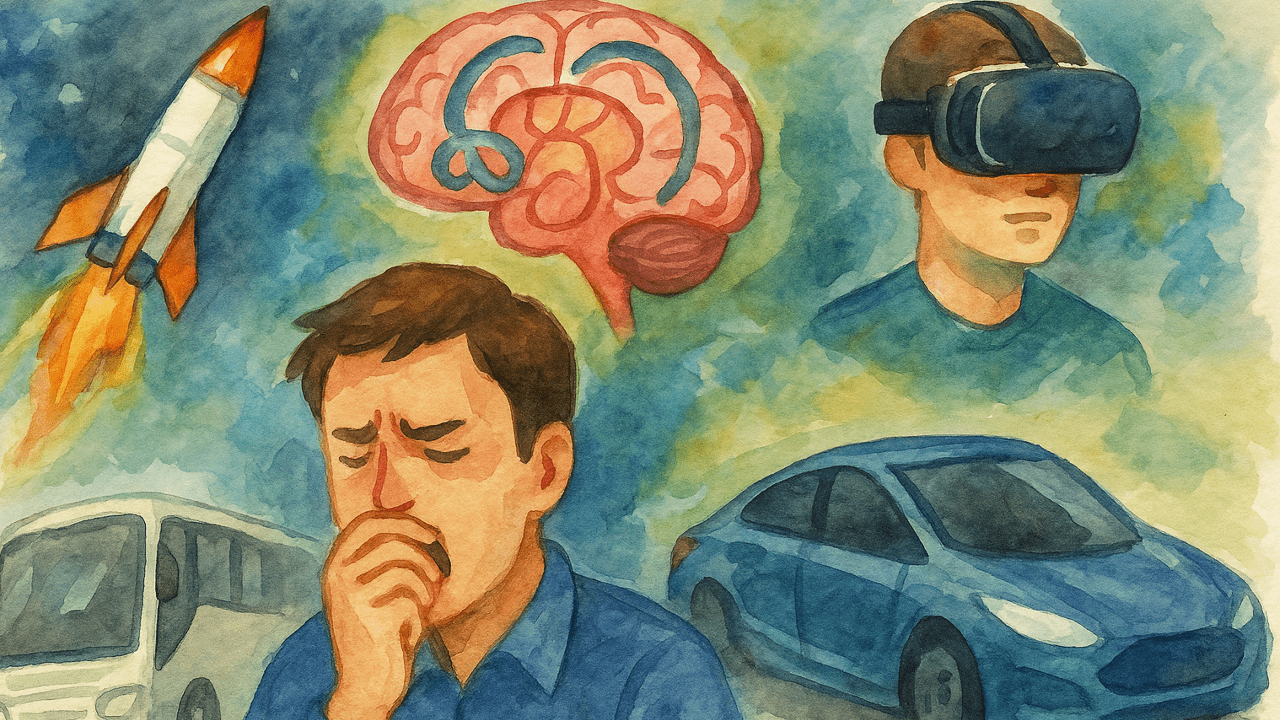
コメント