放送は11月7日(金)16:05〜18:00、NHK総合。ミラノ・コルティナ五輪まで残り3か月、日本代表選考の行方を占うNHK杯男子ショートがいよいよ開幕します。実況は小宮山晃義さん、解説は本田武史さんです。鍵山優真は史上稀な大会3連覇へ、完成度と安定感で主導権を握れるか。佐藤駿は最大の武器・4回転ルッツの出来映え点で差をつけ、初優勝と五輪切符へ弾みを狙います。19歳の垣内珀琉はNHK杯初出場、緊張と高揚のなかで自分の滑りを貫けるかが鍵。短期決戦のSPは冒頭ジャンプの成功率、スピン・ステップのレベル取り、そしてPCSでの加点が勝負を分けます。本記事では滑走順や技術構成の見どころ、ジャッジ傾向、過去大会との比較から“得点の分岐点”を丁寧に読み解き、フリーへの展望までを立体的に解説します。読後には「なぜこの順位になったのか」「どこで明暗が分かれたのか」がはっきり見えるはずです。
- 2025 NHK杯フィギュアスケート男子シングルSP|見どころ完全ガイド
- 注目選手①|鍵山優真 “3連覇”へ向けた挑戦と舞台裏
- 注目選手②|佐藤駿 初優勝めざす4回転ルッツの武器
- 注目選手③|垣内珀琉 19歳の初出場、未知なる可能性
- 出場選手リスト&注目プロフィール|日本&海外勢
2025 NHK杯フィギュアスケート男子シングルSP|見どころ完全ガイド
2025年のNHK杯フィギュアスケートは11月7日(金)から9日(日)まで開催され、会場は東和薬品RACTABドーム。男子ショートは大会初日の午後、注目度の最も高い時間帯に行われます。
今大会の焦点は、北京五輪銀メダリストの鍵山優真が史上稀な三連覇を達成できるか。4回転ルッツを武器に勢いを増す佐藤駿、初出場で挑む19歳の垣内珀琉も注目の的です。それぞれが異なる立場と目的を抱え、氷上で自らの答えを出そうとしています。短いSPの中で勝負を決める要素は、冒頭ジャンプの精度、スピン・ステップのレベル取り、そして演技構成点の加点。シーズン後半や五輪代表選考に直結する大会として、演技内容ひとつひとつが重く響きます。
この大会の位置づけと注目度|五輪代表選考/日本開催の意味
NHK杯はグランプリシリーズ後半戦の日本大会であり、五輪シーズンでは実質的な代表選考の試金石となります。ここでの得点や完成度は、国内外の評価に直結し、シーズン全体の流れを左右します。
特に今季はミラノ・コルティナ五輪まで残り3か月。選手たちは調整段階を終え、本格的なピークに入る時期です。日本開催であることも特別な意味を持ちます。観客の声援は力となる一方、期待の重圧も大きい。緊張感の中でどれだけ平常心を保ち、自分の滑りを貫けるかが勝負の分かれ目です。五輪を見据えた「本番への予行演習」として、すべての要素が問われる大会です。
注目選手①|鍵山優真 “3連覇”へ向けた挑戦と舞台裏
鍵山優真は2025年シーズン、さらなる完成度と安定感を武器にNHK杯三連覇へ挑みます。今季のショートプログラムは「I Wish」。繊細な表現とリズムの抑揚が求められるプログラムで、鍵山の持つ柔軟なスケーティングとスピード感が際立つ構成です。
ジャンプ構成は4サルコウと4トウループ+3トウループのコンビネーションが中心。成功率を高めることと同時に、演技の流れを崩さずに加点を積み上げる設計です。近年の成長は技術面だけでなく精神面にも表れており、演技中の集中力と表現の一体感が年々増しています。
五輪銀メダリストとしての自覚を胸に、どんな状況でも自分の演技をやりきる姿勢が、今年の鍵山を象徴しています。NHK杯のリンクは、彼がこれまで最も力を発揮してきた舞台でもあり、その相性の良さが三連覇の大きな支えになるでしょう。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 氏名 | 鍵山 優真(かぎやま ゆうま) |
| 生年月日 | 2003年5月5日 |
| 出身地 | 神奈川県横浜市 |
| 所属 | オリエンタルバイオ / 中京大学 |
| 身長 | 約160cm |
| スケート開始年 | 2008年(5歳頃から) |
| コーチ | 鍵山正和(父)、カロリーナ・コストナー など |
| 主な実績 | ・2022年 北京五輪 銀メダル(個人) ・2021・2022・2024年 世界選手権 銀メダル ・2024年 四大陸選手権 優勝 ・2024-25 全日本選手権 優勝 |
| 趣味・コメント | 風景写真撮影、音楽鑑賞/「一試合一試合に全身全霊を込めて」 |
| 所属公式サイト | オリエンタルバイオ スケート部公式サイト(所属クラブの公式ページ) |
| 日本スケート連盟プロフィール | 日本スケート連盟 鍵山優真 選手ページ(選手データ・大会情報) |
| X(旧Twitter) | @yuma_kagiyama05(大会報告・オフショットなど) |
| @yuma_kagiyama15(写真・トレーニング風景など) |
注目選手②|佐藤駿 初優勝めざす4回転ルッツの武器
佐藤駿のショートで最大の見どころは、やはり4回転ルッツです。高い基礎点に加えて、流れを殺さない着氷と着氷後のトランジションを噛み合わせる設計ができたとき、出来栄え点が一気に伸びます。助走の長さを最小限に抑えつつエッジの質を保つこと、回転軸を早く立てて空中での姿勢をコンパクトにすること、着氷後に減速せず音楽のアクセントに合わせて次の要素へ接続すること。この三つがそろうと得点の上振れが見込めます。
もう一つの鍵は、リスク管理と加点のバランスです。冒頭の4回転で確実に流れを作れたときは後半のコンビネーションで積極的にGOEを取りにいき、逆に乱れが出たときはリカバリーで失点を最小化しつつスピンとステップでレベルを落とさないこと。ショートは要素数が限られるからこそ、取りこぼしゼロの設計がはっきり勝敗に響きます。
表現面では、加速と減速のコントロールが演技全体の印象を左右します。単に速く滑るのではなく、音楽のうねりに合わせて見せ場を作ること。上体の使い方や視線の運びを整理できれば、PCSのトランジションやインタープリテーションでの伸びしろが残ります。ショート一発勝負の舞台で、4回転ルッツの質と全体設計の精密さが、初優勝への最短ルートです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 氏名 | 佐藤 駿(さとう しゅん) |
| 生年月日 | 2004年2月6日 |
| 出身地 | 宮城県 |
| 所属 | エームサービス/明治大学 |
| 身長 | 約162 cm |
| 主な実績 | 2024 GPファイナル 銅メダル/2024 四大陸選手権 銀メダル ほか |
| 公式プロフィール | 日本スケート連盟 選手ページ |
| 所属チームサイト | エームサービス 公式プロフィール |
| @shunsato_0206 |
注目選手③|垣内珀琉 19歳の初出場、未知なる可能性
初出場の19歳にとって、NHK杯のショートは「自分の現在地を世界基準で測る」最良の機会です。大舞台ではジャンプの完成度より先に、リンクに立った瞬間の佇まいと最初の動作の質が評価を左右します。最初の3歩で氷に乗れるか、最初のターンでスピードとエッジの深さが出るか、演技前半で呼吸が乱れないか。こうした基礎の良さはPCSに直結します。
技術面では、基礎点を欲張りすぎず、確実性の高い構成でGOEを積むことが現実的な戦略です。コンビネーションは着氷後の流れを優先し、回転不足やエッジエラーのリスクを抑える。一方で、ステップのエッジワークや上体の使い方を丁寧に見せられれば、表現と技術の両面で強い印象を残せます。
メンタル面では、ウォームアップから本番までの“自分のルーティン”を崩さないこと。視線の置き方、コーチとのコミュニケーション、リンクイン前の呼吸法まで細部を整えておくと、初出場特有のノイズを小さくできます。結果がどう転んでも、ノーミスの清潔なショートを一度届けられれば、翌日のフリーに向けて大きな自信となり、シーズン後半の伸びしろが一段広がります。未知数だからこそ、観客と審判の記憶に残る可能性があります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 氏名 | 垣内 珀琉(かきうち はる) |
| 生年月日 | 2006年4月18日 |
| 出身地 | 兵庫県西宮市 |
| 所属 | ひょうご西宮FSC |
| 主な実績 | ・2023 JGPハンガリー 銅メダル ・2023 チャレンジカップ 銀メダル ・2024 冬季ユースオリンピック 出場 ・2024 世界ジュニア選手権 出場 |
| @harukakiuchi418 | |
| X(旧Twitter) | @harukakiuchi418 |
| 公式プロフィール | 日本スケート連盟 選手ページ |
出場選手リスト&注目プロフィール|日本&海外勢
エントリーは放送直前まで入れ替えの可能性があるため、一覧は更新前提での体裁にしておくと運用がスムーズです。以下は記事にそのまま組み込める構成例です。
日本勢
鍵山優真 強み:ジャンプの質と流れ、スケーティングの伸び、終盤で失速しない体力設計
見どころ:冒頭4回転の質、スピンとステップの取りこぼしゼロ、音楽解釈の精度
佐藤駿 強み:高難度4回転ルッツ、助走の短さと着氷後の流れ、試合勘の良さ
見どころ:4回転ルッツの出来栄え、リカバリー設計、演技全体の抑揚
垣内珀琉 強み:初出場ならではの推進力、丁寧な基礎動作、伸びしろの大きさ
見どころ:前半の安定感、コンビネーションの質、ステップでの見せ方
海外勢
Boyang Jin(中国) 強み:スピードとジャンプレンジの広さ(例:中国選手として大技を武器にしてきた背景)。
見どころ:中盤の大技配置、PCSの伸び。
Matteo Rizzo(イタリア) 強み:スピンの取りこぼしが少ない、音楽表現の幅。
見どころ:スピンレベルの積み上げ、終盤のまとめ。
Andrew Torgashev(アメリカ) 強み:リンク支配力、ステップの切れ。
見どころ:演技開始直後の加速、ステップのカウントの正確さ。
理由:アメリカ勢の出場予定で、米国記事でも複数言及。
ショートプログラムの技術要件と勝負のポイント|ジャンプ・スピン・ステップ
男子ショートプログラムには、明確に定められた技術要件があります。ジャンプ3種(うち1つはアクセル、1つはコンビネーション)、スピン3種(足替え・姿勢違いを含む)、そしてステップシークエンス1つ。これらの要素で「技術基礎点+出来栄え点(GOE)」を積み上げ、さらにプログラムコンポーネンツスコア(PCS)が加算されます。
勝敗を左右するのは、基礎点の高さよりも“精度”です。ジャンプの着氷が流れているか、スピンの回転数とセンターキープが取れているか、ステップで各エッジを深く刻めているか。これらが全ての評価に波及します。ジャンプの高さや着氷姿勢に目を奪われがちですが、トップ選手の差がつくのはスピンとステップの「取りこぼし率」。小さなミスが積み重なれば2〜3点の差となり、SPでは致命的です。特にレベル4を安定して獲得できる選手は、上位に残る確率が格段に高くなります。
勝負を分ける瞬間とは?冒頭ジャンプ・リカバリー・PCSの鍵
ショートの勝敗は、たった2分40秒の中でいくつかの“勝負の瞬間”によって決まります。その最初の分岐点が冒頭ジャンプ。ここで成功すれば流れが一気に引き締まり、演技全体のリズムが安定します。逆に転倒やステップアウトが出ると、GOE減点だけでなく、次の要素の質やPCSにも影響が出やすいのが現実です。
次に重要なのがリカバリー力。近年の採点傾向では、ジャンプの失敗を演技構成や表現で補える選手が評価されています。瞬時に音楽へ戻る判断力、冷静に構成を組み替える技術が上位常連の条件といえます。
PCS(演技構成点)は、演技の印象を決める「仕上げ」のような存在です。スケーティングスキル、トランジション、パフォーマンス、構成、インタープリテーション――この5項目はすべて積み重ねの結果であり、観客の空気を味方につけるかどうかで数点の差が生まれます。ジャンプが高難度化する今こそ、技と芸術性の両立が問われる時代です。
ホームリンクのプレッシャーと歓声|日本開催ならではの体験
日本開催のNHK杯は、選手にとって“特別な重み”を持ちます。リンクに入った瞬間から感じる観客の熱気、拍手のタイミング、そして静寂の圧力。海外大会とはまったく異なる空気が、氷上の集中力を試します。
鍵山優真にとっては勝ち慣れた舞台でもあり、期待がプレッシャーに変わる微妙な緊張感があります。佐藤駿や垣内珀琉のような若手にとっては、声援が力になる一方で「ミスをしたくない」という意識が強まるリスクもあります。
日本の観客は技術の精度や構成の流れに敏感で、演技の良し悪しをリアルタイムで感じ取る文化を持っています。歓声の質が選手の呼吸を支えることもあれば、静寂がミスを増幅することもある。だからこそ、ホームリンクでは“自分のリズム”を最後まで守ることが最大の課題です。練習通りの滑りを貫いた者だけが、歓声を力に変えられる舞台――それがNHK杯という大会の本質です。
SPからフリーへつながる展望|この順位がどうシーズンを左右するか
ショートの順位は、そのまま翌日の戦い方を規定します。首位発進なら、リスクを最小化した完成度勝負で逃げ切る選択が可能。僅差の2〜3位は、フリーの中盤に“勝負どころ”を置き、加点が波及する配置で逆転を狙うのが定石。中位以降は、クリーンに積み上げながら上位のミス待ちという現実解になります。
ただし、シーズン全体で見ればショートの価値は順位以上です。完成度の高いSPは、そのまま“評価の土台”となり、以後の国際大会でPCSの伸びやすさに反映されます。大崩れを一度でも止められるか、苦しい流れで演技を整え直せるか。こうした“修復力”は年明けの山場で効いてきます。
鍵山優真は、SPでの取りこぼしを抑えたときの再現性が高く、フリーの体力設計まで含めて優位に立ちやすいタイプ。佐藤駿は、SPで4回転の質を見せておくとフリーの高基礎点構成が生き、PCSの追い風も得やすい。垣内珀琉は、まず清潔なSPで自分の“色”を審判に届けることが、フリーの伸びを最大化する近道になります。ショートは結末ではなく、勝ち筋を増やす“設計図”です。

まとめ|鍵山・佐藤・垣内が描く“日本男子フィギュアの新章”
このNHK杯男子ショートは、三者三様の物語が交差します。完成度で主導権を握る鍵山、難度で風穴を開ける佐藤、初舞台で現在地を刻む垣内。勝ち方は違っても、求めるものは同じです。氷に立った瞬間の覚悟、音楽との一体感、最後の一秒まで密度を落とさない集中。
短いプログラムの中で、成功と失敗を分ける差は“たった一動作”。その一動作のために、何百回と繰り返された練習があり、何千歩分のスケーティングが積み上がっています。だからこそ、観る側は点数だけでなく“整ってゆく過程”を楽しめる。
もしこの夜、鍵山が精度で前に出れば三連覇は現実味を帯び、佐藤が4回転の質で会場をさらえば主役交代の兆しが見える。垣内がノーミスで滑り切れば、次の世代の地図が更新されます。NHK杯は、結果を決める場所であると同時に、“次の季節の始まり”を告げる場所でもあります。氷が静止する一瞬、その先に続く物語が確かに動き出す。ここから、日本男子フィギュアの新章が始まります。
氷上に映る「挑戦」という名の物語
フィギュアスケートを観るとき、私たちは得点や結果を追う一方で、そこにある「人の歩み」に惹かれています。NHK杯は、毎年その歩みがもっとも鮮明に浮かび上がる大会です。完成度を求める者、初舞台で殻を破ろうとする者、勝ち負けよりも自分の限界に挑み続ける者。どの選手の滑りにも“物語の種”が宿っています。
鍵山優真の三連覇への挑戦は、単なる記録更新ではありません。彼は故障や環境の変化を乗り越えながら、「技術」と「感情」をひとつの表現に融合させるスケーターへと成長しました。強さは硬さではなく、繊細さと集中の延長線にあることを、彼は滑りで証明し続けています。勝負の中にある静けさ、その背後の努力を知るほどに、彼の演技は“結果を超えた存在”として記憶に残ります。
一方、佐藤駿が見せる4回転ルッツの迫力には、若さの勢いだけでなく、計算された戦略があります。基礎点を最大化しながらも、芸術性を犠牲にしない。そのバランスを探り続ける彼の姿勢は、現代フィギュアの縮図です。難易度の高さよりも、「技をどう生かすか」を問う時代に差しかかっていることを、彼の挑戦が象徴しています。
そして19歳の垣内珀琉。初出場のリンクに立つ若手の緊張は、誰もがかつて通った通過儀礼のようなものです。けれどもそこに宿る純粋さは、観る人の心をまっすぐに揺さぶります。ミスを恐れず、自分のリズムを信じて滑り切る——その潔さこそが未来をつくる原動力です。
今回の記事では語りきれなかった裏側として、NHK杯という大会の“静かな重圧”を触れておきたいと思います。日本開催であることは誇りであると同時に、選手にとって試練でもあります。観客の拍手は温かくも厳しく、ジャッジの視線よりも鋭い瞬間があります。その中で滑る選手たちは、リンクの温度、呼吸の音、氷の抵抗までも感じ取りながら、自らの世界を保ちます。華やかな照明の下には、誰にも見えない「緊張の物語」が息づいているのです。
もうひとつ印象的なのは、世代交代が“対立”ではなく“継承”として描かれていること。鍵山が示す安定感の上に、佐藤や垣内の挑戦が重なり、日本男子フィギュアの層は確実に厚くなっています。ベテランの表現力と若手の爆発力が交錯する構図は、かつて羽生結弦や宇野昌磨が築いた流れを新しい形で受け継いでいる証でもあります。
フィギュアスケートの魅力は、スポーツでありながら“芸術の時間”を共有できることです。勝敗が決まるのは一瞬でも、その一瞬に至るまでの年月が、氷上のすべてに刻まれています。観客は点数を超えた瞬間を見たいのです。スピンが止まる直前の静寂、音楽が途切れる呼吸の間、リンクに響く一歩の重さ——そこに人間の物語が凝縮されています。
NHK杯の夜が終わると、私たちは自然と“次”を想像します。誰が代表になるのか、どの演技が世界に届くのか。しかし、本当の余韻はもっと静かな場所にあります。選手たちがホテルの部屋でスケート靴を外すとき、コーチがノートに小さくメモを残すとき、リンク整備員が最後の氷を磨くとき。大会は終わっても、そこからまた新しい練習の日々が始まる。その連なりの中に、スポーツの真価があります。
NHK杯は、毎年「今、この瞬間の日本男子フィギュア」を映し出す鏡のような存在です。今年もまた、点数以上に語るべき演技が生まれるでしょう。勝者だけでなく、挑戦したすべてのスケーターに敬意を。彼らが残した軌跡は、きっと未来の誰かに受け継がれ、新しい光となって氷上に戻ってきます。
氷が削れる音の奥には、言葉にならない想いが響いています。だからこそ、観る側も心を整えてリンクに向き合いたい。選手たちの滑りを通じて、自分自身の“挑戦する力”を思い出すために。NHK杯は、ただの大会ではなく、努力と継承と希望が交差する「物語の交差点」なのです。
競い合うことで磨かれる、フィギュアスケートという文化
競技としてのフィギュアスケートを語るとき、多くの人は技術や結果に目を向けます。けれども、その奥にある本質は「人が人によって磨かれていくこと」にあります。誰かが挑み、誰かがそれを見て刺激を受け、次にまた別の誰かがそれを超えていく。NHK杯はその循環を最も美しく映す舞台です。鍵山優真が積み上げた完成度を見て、佐藤駿が新しい技術を磨き、垣内珀琉がその背中に憧れながら追いかける。競い合いながらも互いを高め合う構図が、この競技の文化を育てています。
世界のフィギュア界において、日本の存在感は年々増しています。少年期から正確な基礎を叩き込み、演技構成点で高く評価される選手を次々と輩出している国は、実は多くありません。技の難度に加えて、音楽性・振付・身体表現を重視する姿勢が、世界標準を更新し続けているのです。NHK杯のステージは、その「日本的完成度」を国際社会に示す最前線でもあります。観客の声援はその背景を支える力であり、選手が誇りを感じる瞬間でもあります。
鍵山優真が三連覇を狙う中で注目したいのは、彼が常に“観客の時間”を意識して滑っている点です。彼の演技は、点数を取るためだけでなく「心に届く滑り」を設計しています。手の角度や足元の向きひとつまでが音楽と呼吸を合わせ、観る人の感情に語りかける。ジャンプが成功した瞬間だけでなく、音が消える“間”にも物語がある。こうした緻密さが、彼を他のスケーターと区別する最大の理由でしょう。
佐藤駿は、その対極に位置するエネルギー型のスケーターです。勢いで押し切るように見えて、実際には構成の中に綿密な戦略があります。特に4回転ルッツの助走距離、踏切の角度、着氷後の流れを最小限にする計算は、試合ごとに微調整されています。彼の演技には「一撃で観客を惹きつける爆発力」と「ミスの後に冷静に立て直す判断力」が共存しており、それが現代的なフィギュアスケートの象徴といえます。もし今回のNHK杯で彼が完璧なルッツを決めたなら、その瞬間は新しい日本男子の象徴として語り継がれるでしょう。
垣内珀琉は、まだ完成形ではありません。しかしその未完成さこそが魅力です。初出場の舞台では「何かを証明する」よりも「何を感じ取れるか」が重要になります。緊張と期待が入り混じる時間をどう受け止め、次の試合にどうつなげるか。若手選手の数分間は、その後の10年を左右する“始まりの記録”です。観客の目には一瞬でも、本人にとっては一生忘れない時間になるでしょう。
フィギュアスケートは、一度の失敗で終わらない競技です。むしろ、失敗をどう受け入れるかが成長を決めます。ジャンプの失敗は痛みを伴いますが、それを受け止めた瞬間、次への課題が見えます。氷に刻まれた小さな傷跡こそ、選手が前へ進む証。完璧な演技よりも、立ち上がる力が人の心を動かします。NHK杯という舞台には、その「再挑戦の物語」が必ず存在します。
この大会のもう一つの魅力は、テレビ越しでも“空気の密度”が伝わることです。照明が落ち、静寂の中で流れる音楽。カメラが選手の表情を捉えた瞬間に、息遣いや心拍の速さまでもが感じ取れる。観客席の拍手や息をのむ音が、ひとつの“共演”として演技を支えます。日本の観客が持つ“間”の文化は、海外の解説者にも称賛されるほどで、その雰囲気が選手の集中を助ける要素にもなっています。
また、NHK杯は競技であると同時に“教育の場”でもあります。若い選手たちはトップ選手の演技を見て、氷上の立ち振る舞い、緊張との向き合い方、演技後の礼の仕方までを学びます。リンクの外での姿勢が、そのまま技術の成熟へとつながることを、彼らは知っています。競技を超えて「人格が磨かれる場所」として、NHK杯の存在は世代を超えた影響を与え続けています。
この競技は、記録よりも“記憶”で語られることが多いスポーツです。高得点が出た瞬間よりも、演技後の静かな涙、観客が総立ちになる瞬間、コーチがそっと肩を叩く場面の方が、強く心に残る。NHK杯の歴史を紐解けば、そうした記憶の積み重ねが日本フィギュアの成長そのものを物語っています。
そして、氷が解けるように一夜が終わったあとも、選手たちの挑戦は続きます。翌朝にはすでに新しい目標があり、次の練習が始まる。努力の軌跡は途切れません。観客にできることは、その連なりを見守り、拍手で返すこと。それが、フィギュアスケートという文化を支える最も誠実な形です。
このNHK杯もまた、新しい名場面を生むでしょう。鍵山の正確さ、佐藤の勇気、垣内の情熱。三者三様の軌跡が交差するとき、そこに“日本男子フィギュアの未来図”が見えてきます。競い合いながら支え合い、挑戦しながら進化していく。その姿は、私たちの日常にも通じる普遍のテーマです。だからこそ、氷上の3分間に心を重ねる観客が絶えないのです。
フィギュアスケートは、終わるたびに始まります。リンクの上で生まれた一瞬の輝きが、次の世代の原動力となり、また新しい挑戦を呼び起こす。NHK杯は、その連鎖の中心にある「希望の灯」です。今年もその光が、きっと誰かの心に届くでしょう。

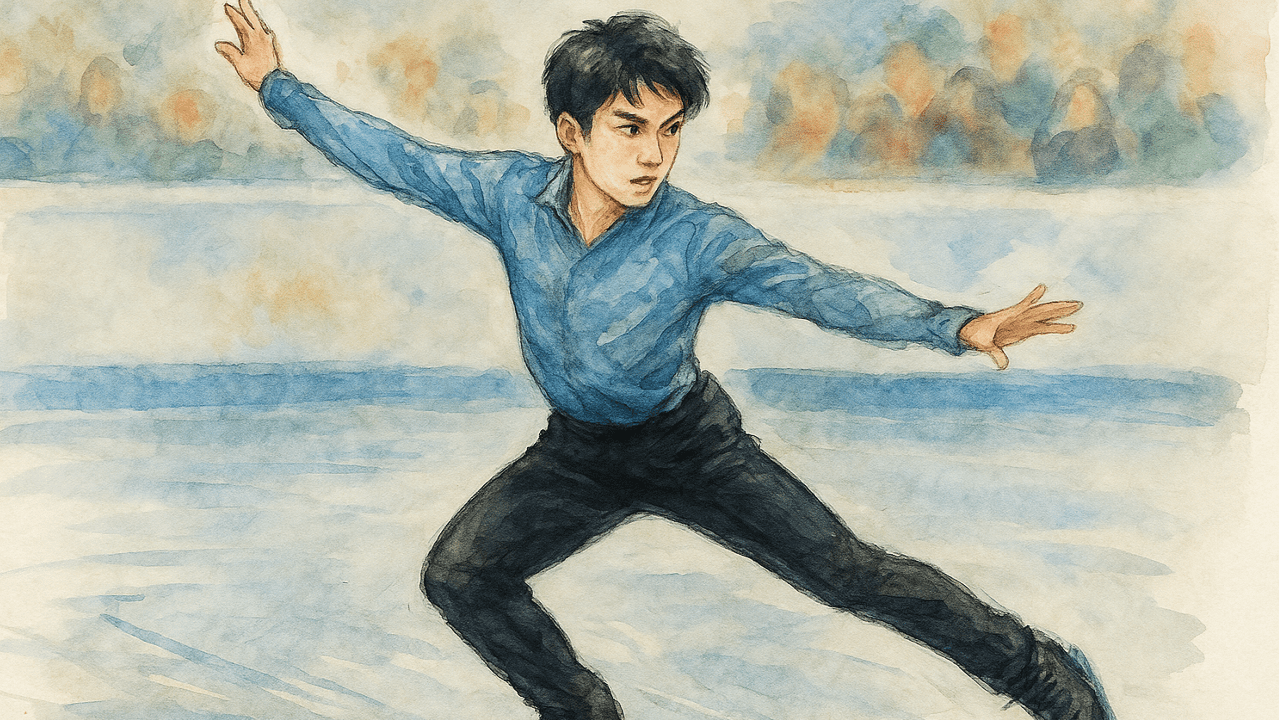
コメント