NHK Eテレで放送される「カールさんとティーナさんの古民家村だより」は、雪深い新潟県十日町市松代を舞台にした番組です。舞台となるのは竹所集落に残る古民家群で、その中心にあるのがカールさん夫妻が手を入れた「双鶴庵」です。ドイツ出身の建築家カール・ベンクスさんと妻のティーナさんは、この地に根を下ろし、カフェを営み、古民家の再生を通じて地域の文化や暮らしの魅力を伝えています。番組では古民家を守り生かす工夫や、村の人々との温かな交流が描かれており、視聴者に日本の伝統と未来の暮らし方を考えるきっかけを与えてくれます。
所在地情報とアクセス案内
澁い – SHIBUI – 古民家カフェ 住所と所在地
住所 〒942-1526 新潟県十日町市松代2074-1
電話番号 025-594-7944
公式サイト https://karl-bengs.jp/shibui/
営業日 営業日カレンダー (木・金・土・日・祝日・不定休や貸切あり)
営業時間 11:00~16:00 ランチL.O. 15:00 ドリンクL.O. 15:30
メニュー https://karl-bengs.jp/menu/
駐車場 あり https://karl-bengs.jp/parking/
双鶴庵
〒942-1356 新潟県十日町市竹所
竹所 古民家再生の里 https://karl-bengs.jp/taketokoro/
カールさんとティーナさんの古民家「双鶴庵」が位置するのは、新潟県十日町市松代の竹所集落です。十日町市の中心部から車でおよそ30分、最寄り駅は北越急行ほくほく線の「まつだい駅」です。まつだい駅からは車で20分ほど山間部へ進むと竹所集落に到着します。
アクセスの方法としては、公共交通機関を利用する場合、まず北陸新幹線の越後湯沢駅まで移動し、そこからほくほく線に乗り換えて「まつだい駅」へ向かいます。駅から先はバス便が少ないため、タクシーかレンタカーの利用が便利です。自動車の場合は国道253号線や403号線を経由して松代方面に入り、集落の案内板を頼りに進むとたどり着けます。
竹所集落は豪雪地帯にあるため、冬季は道路の積雪や除雪状況に注意が必要です。スタッドレスタイヤやチェーンを備えて訪れることが望ましく、事前に道路情報を確認することが安全につながります。
カールさんの澁い – SHIBUI – という古民家カフェや、観光スポットとして星峠の棚田、松之山温泉などもあり、古民家の見学と合わせて訪れると充実した旅程になります。特に星峠の棚田は朝霧に包まれる風景が美しく、写真愛好家に人気の場所です。松之山温泉は日本三大薬湯のひとつに数えられ、観光客に癒やしを提供しています。
このように竹所集落と双鶴庵と澁い – SHIBUI – 古民家カフェは、新潟県十日町市を訪れる際に一度は足を運びたい場所といえます。歴史を感じる古民家と自然豊かな風景を同時に体験できることは、訪れる人にとって大きな魅力となっています。
「双鶴庵」と古民家群の特徴
双鶴庵は新潟県十日町市松代の竹所集落にある再生古民家です。雪国の暮らしに根ざした家づくりが色濃く残り そして現代の生活に必要な快適性も丁寧に織り込みます。外観は周囲の山里の風景に溶け込み 内部は木の質感が落ち着きを生みます。太い柱や梁が空間を支え 風や湿気の通りを乱さない配慮が感じられます。断熱や耐震への備えを相性の良い素材と納まりで整え 古材を傷めずに生かす姿勢が一貫します。雪の負荷に配慮した屋根の掛け方や庇の出方に無理がなく 日常の手入れを続けやすい形に整えます。照明や水まわりは控えめで扱いやすく 家事や来客の動線が分かりやすい計画です。竹所には双鶴庵以外にも再生古民家が点在し 集落を歩くと建物ごとの個性と共通点が見えてきます。周囲の畑や里山の眺めと建物の佇まいが響き合い 滞在そのものが学びになります。地域の季節行事や日々の作業と住まいが無理なくつながり 暮らしの道具や収納の置き方にも秩序が行き渡ります。過度な装飾に頼らず 手を入れた痕跡が静かに語る家です。
カール・ベンクスさんのプロフィール
カール・ベンクスさんはドイツ出身の建築家です。日本の古民家に宿る技と美しさに敬意を払い そして住まいとしての使いやすさを損なわない再生を続けてきました。拠点は十日町市松代に置き 地域の職人と協力して実務を積み重ねます。設計は古材を尊重し 新たに加える要素は静かに引き下がる姿勢です。構造に無理をかけず 断熱や耐震の改善を丁寧に積み上げます。意匠は素材の質を引き立て 生活のリズムを邪魔しません。住まい手の暮らし方を聞き取り 片付けや掃除が続けやすい寸法と動線を整えます。地域の山や川や田畑に目を配り 材の産地や経年の表情を読み取ります。若い世代と職能の橋渡しにも力を注ぎ 古民家の価値を地域の言葉で伝えます。海外にルーツを持ちながら 地域の一員として地道に働く姿勢が評価され 相談の輪が自然に広がります。華美な演出より 長く住める納まりを優先し 小さな不具合を見逃さない実務家です。暮らしに効く寸法と手順を重んじ 住む人が主役であるという考えを一貫して守ります。
ティーナさんのプロフィールと活動
ティーナさんはカールさんの伴走者であり 現地と来訪者をつなぐ要です。地域の習わしに敬意を払い そして初めて訪れる人にも分かりやすい案内を心掛けます。家事や来客の段取りに無理が出ないように 動線や置き場をきめ細かく整えます。季節の手入れや保存の段取りに寄り添い 日々の小さな変化に気づきます。説明はやわらかく 生活者の目線で言葉を選びます。掃除や洗濯や片付けの手順を無理なく続けられる形に落とし込み 住まい手が自分のやり方を見つけられる余白を残します。地域の方との交流では 相手の時間に合わせて歩調を合わせます。来訪者にはこの土地の気候や道の事情を分かりやすく伝え 安全と安心を最優先に案内します。食やしつらえの所作は素朴であり もてなしの心が滞在の体験を豊かにします。説明しすぎず 押しつけず 相手の関心に耳を澄ませる姿勢が印象に残ります。再生した家が長く愛されるには 日々の営みが無理なく続くことが要であり そのための工夫を静かに積み重ねる実務の人です。
二人の人柄に触れるエピソード
お二人の印象は誠実と節度です。初対面でも声を荒らげず そして相手の言葉を最後まで聞きます。家について語るときも 音や匂いのような生活の感覚を大切にします。何かを足す前に すでに在る良さを確かめます。作業の現場では道具の置き方に無駄がなく 片付けと掃除が次の工程を助けます。来訪が重なる日でも 歩く速度を落とし 足元と天井と壁の順に視線を誘導します。家に触れる手つきは穏やかで 角を傷めぬように布を添えます。地域の集まりでは大声で目立たず 必要な役回りを淡々と引き受けます。雪の季節は無理をしない原則を守り 作業は小分けにし 体力と時間を配分します。説明で行き詰まると すぐに見本を示し 相手の手を止めない配慮を欠かしません。評価や名声の話題より 暮らしや健康の話題を先にします。別れ際には次の季節の注意を簡潔に伝えます。住まいは完成で終わらず 手入れが続くからです。静かな所作が信頼を積み重ね 訪ねた人は肩の力が抜けます。家が主役で 人がそれを生かすという姿勢が一貫します。
番組が伝えるメッセージ
この番組が伝える中心は 古い家を残すことが目的ではなく 暮らしを受け継ぐ姿勢そのものです。柱や梁には人の手の跡が残り 家事や仕事の動線には地域の知恵が息づきます。だからこそ直す前に確かめ そして無理をせず生かすという視点が重なります。雪に耐える屋根や庇は自然に寄り添い 住む人の体の動きに合う寸法は健康と安全を守ります。直して終わりではなく 手入れを続ける段取りを整えることが本当の再生です。番組はこの当たり前を丁寧に映し 住まいは人を待ち受ける器であり 人が器を育てる関係だと教えてくれます。地域の行事や食の支度や掃除の順番は派手ではありません。けれども季節を重ねるほど暮らしに芯が通ります。子どもにも分かる言葉で仕組みを解き 明日から真似できる所作へ落とし込みます。古民家は特別な舞台ではなく 住み続けられる家であるべきだと示し そして地域と外から来た人が対等に学び合う場になることを静かに伝えます。
舞台となる新潟県十日町市松代・竹所集落
十日町市は新潟県の南部に位置し、日本有数の豪雪地帯として知られています。その中でも松代地域の竹所集落は、古民家が数多く残るエリアとして注目を集めています。竹所は山あいにある小さな集落で、昔から雪と共に暮らす知恵が培われてきました。屋根の形や建材の選び方には雪国ならではの工夫が見られ、長い年月を経てもなお地域の人々を守り続けています。
この集落が広く知られるきっかけとなったのが、ドイツ出身の建築家カール・ベンクスさんの活動です。カールさんは荒れた古民家を買い取り、現代の生活に合わせながらも伝統を壊さない形で再生しました。その代表例が「双鶴庵」であり、現在では集落の象徴ともいえる存在となっています。再生された古民家は単なる住居ではなく、地域の文化を発信する拠点としても活用されています。
竹所集落には「イエローハウス」などの再生古民家も点在しており、訪れる人にとっては集落全体が古民家の博物館のように映ります。また、澁い – SHIBUI – という古民家カフェも近隣にあり、再生古民家を実際に体験できる場として人気を集めています。
地域では「大地の芸術祭」と呼ばれる国際的なアートイベントも開催され、集落とアートが融合する景観は独特の魅力を放っています。竹所を訪れることで、雪国の厳しい環境で磨かれた暮らしの知恵や、古民家の美しさを実際に感じることができます。竹所は単なる田舎の集落ではなく、古民家再生と地域文化の継承を同時に実現している貴重な舞台なのです。
古民家村だよりと地方創生
地方創生は新しい施設を増やす話に偏りがちです。番組が示す道筋はまず在る資源の価値を見直し そして暮らしの手順を整えることです。古民家は観光資源に見えますが 本質は日常の積み重ねです。雪が降る前に屋根の点検を済ませ 乾きやすい動線で洗濯を回し 保存食を季節に合わせて仕込みます。こうした仕事が自然と共有されれば 高齢の方も子どもも同じ輪に入れます。訪れる人が増えれば空き家の再生に活路が生まれ 地元の木や職人に仕事が循環します。短期の話題づくりではなく 学びの場として関係人口が育ちます。移住希望者には冬の備えと交通の現実を正確に伝えます。無理をせず できる作業から始めれば定着率は上がります。近隣の温泉やアート拠点と結び 宿泊と体験を組み合わせれば滞在は伸びます。売るより伝える姿勢が信頼を生み リピーターが地域の応援者になります。番組はこの地道な循環を可視化し そして地域の言葉で語ることで実感を伴う手本を提示します。
所在地周辺の観光情報
拠点の竹所集落を起点に 体験と学びがつながる周遊が組めます。**大地の芸術祭 越後妻有アートフィールド**は屋外作品が里山に点在し そして会期外も鑑賞できる場所が多くあります。作品に向かう道のり自体が風景の講座になり 農とアートが溶け合う体験になります。まつだい「農舞台」は展示と学びの機能を備え 建築空間の中で地域の視点に触れられます。休憩や情報収集の拠点としても使いやすく 旅のリズムが整います。松之山温泉は日本三大薬湯として知られ 湯あたりが力強く 体を芯から温めます。積雪期の冷えでこわばった体にやさしく そして移動の疲れをほぐします。星峠の棚田は早朝や夕刻で表情が変わり 霧や水鏡が季節を映します。撮影時は私有地に配慮し 三脚の設置と駐車の位置に注意します。雪国の郷土料理体験では ふのりでつなぐへぎそばや きのこや山菜の素朴な味に出会えます。塩や出汁の加減は雪国の保存の知恵に基づき 体を温めます。各地に小さな直売や食堂があり 人の勧めに従うと外れが少なく なにより会話が旅の記憶を濃くします。移動は天候に左右されやすいため 早出早着を心がけ 無理のない距離で計画すると安全です。
古民家再生に興味を持った人へのガイド
まず見学は連絡と時間調整が基本です。住まいは暮らしの最前線ですから 受け入れの準備に配慮します。靴の扱いと手荷物の置き場は案内に従い そして撮影は人と私物が写らないように注意します。扉と建具はゆっくり扱い 戻す位置を守ります。床は無垢材が多く 水滴や砂は傷の原因になります。飲み物はふた付きが安全です。冬季は道路と駐車の条件が変わります。スタッドレスタイヤの装着を基準にし 早朝や夕刻の峠越えは避けます。訪問前に除雪状況を確かめ 無理な進入は控えます。学びを深めたい方は小さな手入れから始めます。掃除の順番や収納の置き換えや採光の調整は費用をかけず効果が出ます。次に断熱と気密の要所を理解し 風通しと結露の関係を把握します。専門工事は地域の職人と相談し 家の履歴を記録します。図面や写真や費用の過程を残せば 次の手入れに役立ちます。移住を検討する方は季節ごとの暮らしを体験します。短期の滞在で雪と向き合い 物資の買い出しや通院の段取りを試し 生活の手応えを確かめます。焦らず合う家と地域を選べば 長く続く再生になります。
カールさんとティーナさんの挑戦が示す未来
お二人の挑戦は古民家を美しく見せる活動ではありません。暮らしを続ける力を家に取り戻す実務です。雪と湿気に向き合い 使い手の体の動きに合う寸法を整えます。手入れが続く順番を決めて 無理なく守れる方法に落とし込みます。道具は増やさず 必要な物を定位置に置きます。記録は写真とメモで残し 次の手入れの起点にします。地域の職人と学び合い 技の流れを絶やさない仕組みをつくります。若い世代には掃除と採光と風の通りを体で覚えてもらいます。来訪者には安全と礼儀を先に伝え 住まいへの敬意を共有します。観光と暮らしを混ぜすぎず 日常を土台に据えます。外から持ち込む解決策は最小にして 地の素材と人の力を生かします。移住の希望者には季節の現実を正確に伝えます。冬の段取りが整えば安心が生まれます。安心が生まれれば関係が続きます。続く関係が地域を支えます。お二人の挑戦は特別な舞台ではなく 同じ条件で誰もが取り組める道筋です。だから未来は遠い場所ではありません。明日の手入れから始まる身近な営みです。
NHK Eテレ「古民家村だより」とは?
NHK Eテレ「カールさんとティーナさんの古民家村だより」は、教育番組として放送されているシリーズで、日本各地に息づく伝統文化を紹介する中でも古民家に焦点をあてた内容となっています。この番組は単に建物を紹介するだけでなく、そこに暮らす人々の姿や地域に伝わる知恵を分かりやすく伝えており、視聴者に「暮らしを守ること」の大切さを感じてもらえる構成になっています。
舞台は新潟県十日町市松代地区の竹所集落で、雪国の厳しい環境に建てられた古民家を再生した「双鶴庵」を中心に撮影が行われています。双鶴庵は築およそ百年以上の木造住宅で、地域の歴史を背負いながら現代の暮らしに合わせた改修がなされており、その佇まいは古さと新しさの調和を感じさせます。
番組では建物の紹介にとどまらず、カールさんとティーナさんが日々どのように古民家と向き合い、地域の方々と関わっているかが丁寧に描かれます。冬には雪下ろしや保存食作り、春から秋にかけては田畑の手入れや祭りへの参加など、暮らしの一部をそのまま視聴者に伝えています。
特に教育番組らしく、古民家の構造や素材の特徴を解説する場面が盛り込まれており、土壁や梁の役割、雪に耐えるための工夫などが紹介されます。子どもから大人まで楽しめるように作られており、古民家を通じて日本文化を多世代に伝えるという目的が明確です。こうした点から「古民家村だより」は、地域の生活と文化を体感できる貴重な番組であるといえます。
まとめ|古民家から広がる暮らしの可能性
古民家は古さを愛でる対象ではありません。日々の家事が回り 人と季節が整う器です。番組はその当たり前を丁寧に映します。柱や梁は時間を語り 壁や床は手入れの跡を語ります。お二人は急がず そして飾らず 改善の順番を重ねます。屋根の点検と通風の確保と掃除の徹底は大きな工事に先立つ要です。訪れる人が守る作法は次の訪問者を守ります。地域の店や温泉やアートの拠点は学びの道を延ばします。観光の賑わいは目的ではありません。関係が続く仕組みが目的です。住み手は自分の暮らしを整え 見学者は礼を尽くし 職人は技をつなぎ 学校は体験を授けます。誰もが担い手になります。古民家は過去の象徴ではなく 未来の練習場です。明かりの高さと手の届く収納と濡れを拭く布が暮らしを支えます。今日の一手が明日の安心につながります。読者の皆さまも自分の家の一角から始められます。埃を払って風を通し 光を受けて物の定位置を決めます。小さな一歩が暮らしを変えます。古民家が教えるのは住まいが人を待ち 人が住まいを育てるという確かな関係です。
古民家と暮らしの知恵に学ぶ
新潟県十日町市松代の竹所集落に足を運ぶと、雪深い環境と共に生きてきた人々の息遣いを感じます。古民家は単なる建築物ではなく、長い歴史の中で育まれた暮らしの知恵そのものです。番組「カールさんとティーナさんの古民家村だより」を通じて、古民家の価値を改めて考えることができました。そこには単なる保存ではなく、未来に引き継ぐための実際的な努力がありました。
カールさんとティーナさんは、異国からやってきてこの土地に根を下ろし、地元の人々と共に古民家再生に取り組んでいます。その姿は「外から来た人」という立場を越え、「村の一員」として受け入れられていることを示しています。地域の人々もまた、お二人の誠実な姿勢を感じ取り、自然と協力の輪が広がったのだと思います。人柄や言葉選び、そして日常の立ち居振る舞いが信頼を育ててきたことが伝わってきます。
双鶴庵のたたずまいを見ると、古民家の力を実感します。太い柱や梁は、雪の重みに耐えながら家族の暮らしを支え続けてきました。その骨格を大切に生かしながら、断熱や耐震といった現代の工夫を加える。新しいものを全面に押し出すのではなく、もともとある良さを引き立てる形で再生することに意味があるのだと気づかされます。古民家は過去の遺物ではなく、今を生きる人々の生活の舞台として力を持ち続けているのです。
また、番組を見て感じたのは「暮らしの手入れを続けることの大切さ」です。掃除や片付け、雪下ろし、保存食づくりといった日常の営みが、実は古民家を長く保つ力になっています。大きな工事よりも、日々の小さな積み重ねが建物を守ります。この考え方は、現代の住まいに暮らす私たちにも通じることです。便利さを追い求めるあまり、日常の手間を省こうとする傾向がありますが、実はその「手間」こそが暮らしを豊かにし、安心を支えているのではないでしょうか。
竹所集落は、古民家再生と地域文化の発信が一体となった場所です。集落を歩くと、再生された家々が点在し、それぞれが個性を持ちながらも共通の美しさを放っています。その姿は、地域全体がひとつの「生きた博物館」のようです。同時に、住む人々の生活の場でもあるため、展示品のように触れられない存在ではなく、今も息づく文化として体験できます。この「生きている文化」に触れることが、訪れる人に深い学びを与えているのだと思います。
さらに、この地域を訪れる魅力を広げているのが周辺の観光資源です。大地の芸術祭 越後妻有アートフィールドでは、自然とアートが融合した景観を楽しめます。松之山温泉は、厳しい冬の寒さを癒やす力強い湯として知られています。星峠の棚田は、朝霧や夕日の光に照らされて幻想的な姿を見せてくれます。こうした観光と古民家の体験が結びつくことで、地域全体の魅力が増し、人々を呼び寄せているのだと感じます。
地方創生という言葉はよく耳にしますが、竹所集落の取り組みにはその本質があるように思います。新しい施設や大型プロジェクトに頼るのではなく、既にある資源を大切にし、それを今の暮らしに合わせて使い続ける。その姿勢が持続可能な地域づくりにつながっています。訪れる人は観光客であると同時に、学びを持ち帰る存在です。そして再び訪れることで、地域との関係が深まります。この循環こそが真の地方創生だと感じます。
カールさんとティーナさんの挑戦は、古民家を通じて「持続可能な暮らしのかたち」を実践している点に価値があります。海外出身であるカールさんが日本の古民家に深い敬意を払い、その美しさと合理性を伝えている姿には、文化を超えた普遍的なメッセージがあります。ティーナさんの柔らかい人柄と実務的な支えがあってこそ、この挑戦が成り立っていることも忘れてはならない要素です。お二人が地域に溶け込み、外から来た人と内にいる人をつなぐ存在になっていることが、古民家再生の取り組みをより確かなものにしています。
最後に、この番組や活動を通じて私が強く感じたのは、「古民家は未来の練習場である」ということです。過去を尊ぶだけではなく、今を生きる私たちが学び、次の世代につなぐための場です。風を通し、光を受け、掃除を続け、手入れを怠らない。その一つ一つが未来への種まきです。私自身も、自分の身近な暮らしにおいて、小さな一歩から始めることができるのではないかと感じています。
古民家は人を待ち、人が古民家を育てる。その関係性が続く限り、地域は生き続けるでしょう。カールさんとティーナさんが見せてくれる姿勢は、私たちにとって大切な指針です。大きなことを成し遂げようとするのではなく、目の前の暮らしを整え、日々を丁寧に生きる。その積み重ねが未来を形づくるのだと、改めて気づかされました。
古民家に映る学びと静かな循環
雪国の山あいに佇む古民家を訪れると、まず耳に届くのは静寂です。竹所集落の家々は雪の重みを受け止めるようにどっしりと構え、壁や梁は時の流れを語りかけます。NHK Eテレの番組「カールさんとティーナさんの古民家村だより」を通じてその姿を目にすると、私たちが忘れかけている暮らしの原点が鮮やかに浮かび上がります。古民家は過去を保存する装置ではなく、今を生きる人々を支える器であることを静かに示していました。
この番組の大きな魅力は、住まいを舞台に人の営みが丁寧に描かれる点です。雪が降れば屋根を守る作業があり、季節が巡れば畑を耕し収穫を喜ぶ姿があります。その一つひとつが古民家を支える力になっています。私自身、便利さを追い求めがちな日常の中で、こうした「手をかける暮らし」の価値をあらためて思い知らされました。
カール・ベンクスさんはドイツ出身の建築家ですが、彼の歩みは単なる異文化交流を超えています。日本の古民家に宿る合理性を正確に理解し、それを現代の生活に生かす姿勢は、学ぶべき誠実さを感じさせます。断熱や耐震といった改修は安全に欠かせませんが、それを押し付けがましくなく、もとの家の表情を尊重しながら進めているのが印象的です。古民家を新しい観光資源に変えるのではなく、住み続けられる住まいに整える。その姿勢が、地域と外からの訪問者の双方に安心を与えています。
ティーナさんの存在も見逃せません。家事や訪問者の案内といった日常の営みの中で、相手を思いやる気遣いが伝わります。来客が戸惑わないように導き、地域の方と歩調を合わせ、食卓やしつらえに心を込める。そうした営みが再生された家を単なる建築物ではなく「暮らしの舞台」に変えていきます。言葉や所作が柔らかく、押しつけを感じさせないからこそ、多くの人が自然と心を開くのでしょう。
双鶴庵を含む竹所集落の古民家群は、地域の記憶を伝える「生きた博物館」のようでもあります。しかし展示品とは異なり、そこには火があり、食卓があり、人の笑顔があります。訪れる人は文化財を見物するのではなく、いまも続く暮らしを体感することができます。その実感が、多くの学びを生み出しているのだと思います。
周辺に広がる観光資源との結びつきも大きな魅力です。大地の芸術祭 越後妻有アートフィールドでは、自然の中に点在する作品が訪問者の感性を揺さぶります。松之山温泉は厳しい寒さを癒やし、星峠の棚田は四季折々の美しい景観を見せてくれます。これらと古民家体験が一体となることで、旅は単なる観光にとどまらず、地域全体を味わう豊かな学びへと広がります。
地方創生という言葉はしばしば経済効果や移住促進の文脈で語られますが、竹所集落の姿はもっと実直です。空き家を蘇らせることは観光資源をつくる手段ではなく、暮らしを守り続けるための基本です。地域の人が日々の営みを積み重ね、それを訪れる人が尊重する。結果として交流が生まれ、関係が深まり、持続可能な循環が育まれます。ここにあるのは派手な仕掛けではなく、静かで確かな営みです。
私が特に心を打たれたのは「手入れを続ける暮らしの姿勢」です。掃除や点検、季節ごとの準備は大変なように見えますが、それこそが安心を生みます。未来を考えるとき、大きな投資や新しい技術ばかりに目が行きがちですが、実際には毎日の積み重ねが暮らしを支えているのです。この考え方は古民家に限らず、どんな住まいにも通じる普遍的な知恵だと感じました。
カールさんとティーナさんの活動を見ていると、文化の壁や国境を越えた普遍性を強く意識します。暮らしを大切にする姿勢、手をかけて続ける努力、人との関係を尊重する心。それらは国籍や立場に関係なく共感を呼ぶものです。むしろ外から来たからこそ気づける視点と、内にいるからこそ守れる知恵が交わり、新しい形を生んでいるのだと実感します。
古民家は過去を懐かしむだけの存在ではなく、未来を築くための練習場でもあります。屋根に積もる雪を降ろす動作や、梁を拭く手間や、窓を開けて風を通す習慣。そのすべてが未来への備えであり、次の世代への贈り物です。番組を通して見えたお二人の姿勢は、誰もが自分の暮らしの中で実践できる小さな手がかりを与えてくれました。
私自身、この番組に触れてから、自宅の窓を少し長く開けて風を通すようになりました。小さな習慣ですが、それが家を整える一歩であると信じることができます。古民家に宿る知恵は、特別な家だけでなく、日常のすぐそばに応用できるものなのです。
竹所集落の古民家に込められた思いは、これからも人々の学びの場であり続けるでしょう。地域の人と外からの訪問者が共に支え合い、暮らしを通じて未来を考える。その姿は、静かでありながら力強い循環を示しています。
「古民家は人を待ち、人が古民家を育てる。」この言葉に尽きるように思います。お二人の活動は、その当たり前を改めて教えてくれる道しるべでした。これから先、私たちが日々の暮らしにどのように手をかけ、どのように人と関わっていくのか。その答えは、竹所の古民家とそこに暮らす人々の姿の中に静かに示されているのだと感じます。
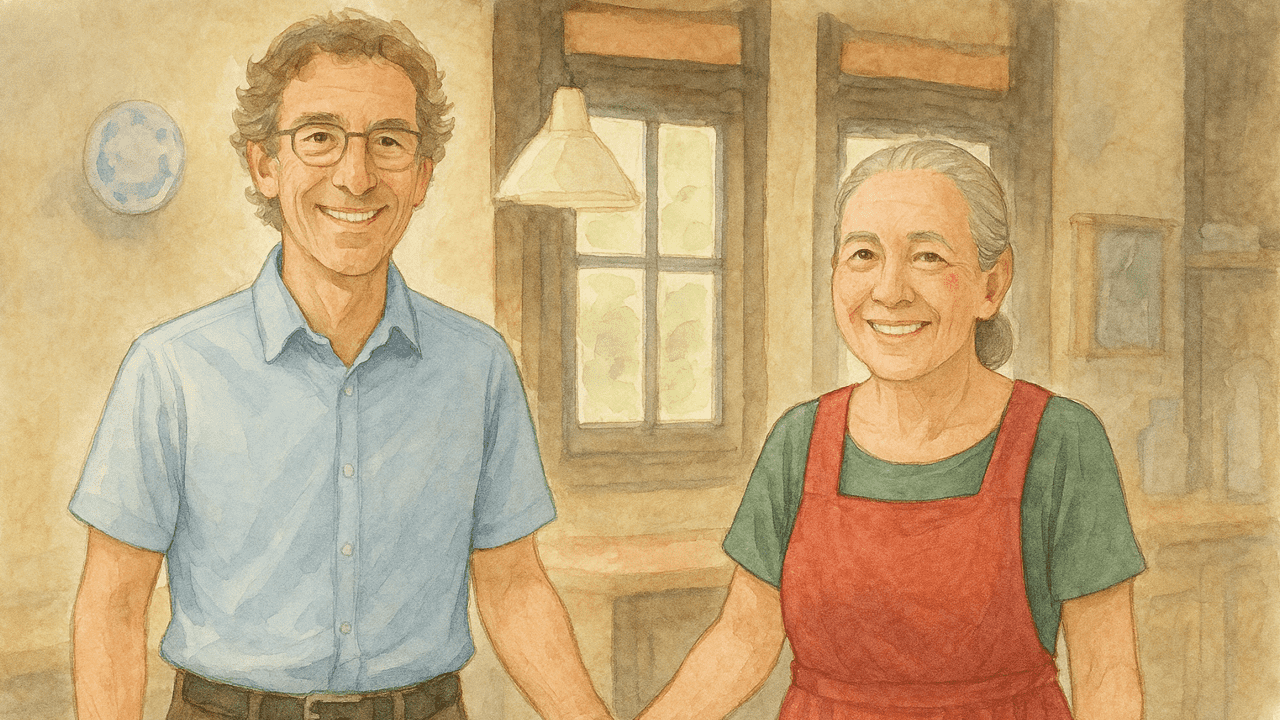
コメント